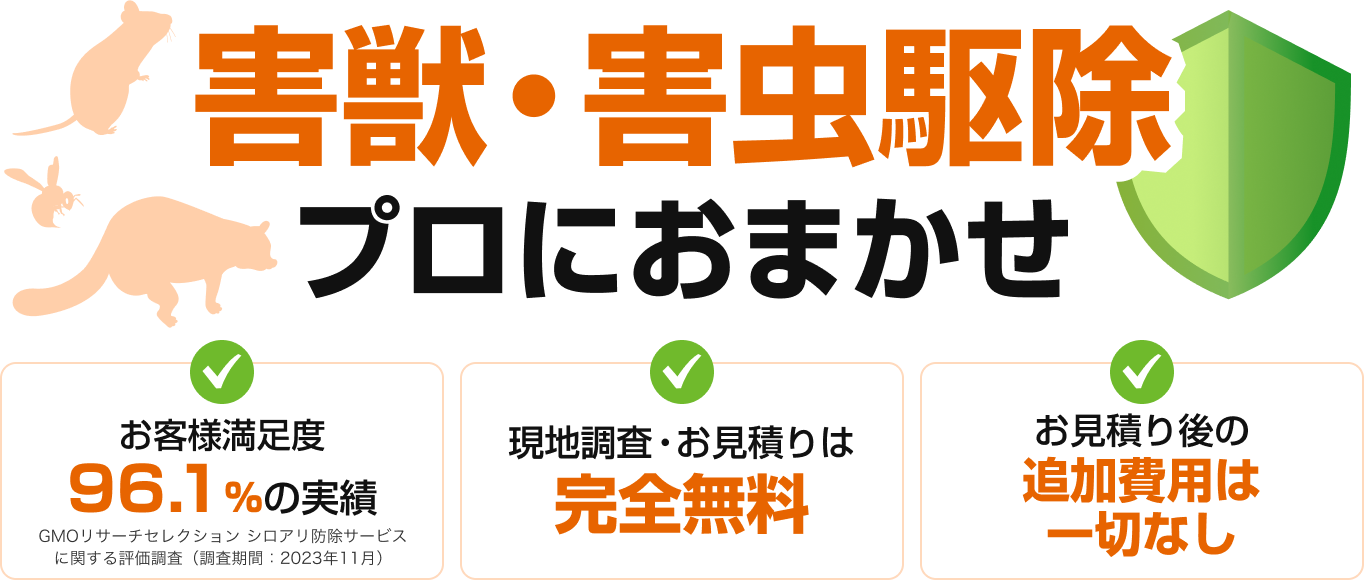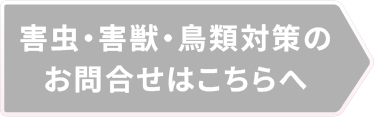ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ネズミ > ネズミの侵入経路がわからないときの対処法|よくある侵入経路と特定方法も解説
ネズミの侵入経路がわからないときの対処法|
よくある侵入経路と特定方法も解説

近年、都市部や住宅街ではネズミによる被害が広がっています。天井裏や壁から物音がしたり、食品の袋がかじられていたりするにも関わらず、どこからネズミが入り込んでいるのかわからないというケースは少なくありません。
これは、ネズミの侵入経路は目立ちにくい場所にあることが多く、家の構造やネズミの習性の複雑さが原因で発見が難しいことが原因の一つです。
本記事では、ネズミの侵入経路が特定できない主な理由やよくみられる侵入パターン、さらに侵入経路の見つけ方や相談先まで詳しく解説します。自力での対処が難しい場合の対処法も解説しますので、被害の拡大を防ぐための参考にしてください。
ネズミの侵入経路がわからない3つの理由
ネズミの気配に気づいても、どこから入ってきているのか突き止められないことは珍しくありません。被害が続いているにも関わらず侵入経路がわからないのは、ネズミの特徴や行動の習性が関係しています。
この章では、ネズミの侵入経路が特定しづらい主な理由を3つ紹介します。
わずかな隙間でも侵入できるから

ネズミは、体を柔軟に変形させて狭いすき間にも入り込むことができます。クマネズミは1.25cm、ハツカネズミは1cm(10円玉の半分の大きさ)程度のすき間があれば建物内へ侵入可能といわれており、外壁の亀裂や配管まわりのわずかな隙間でも通り抜けてしまいます。外からは気づきにくい細い穴でも、ネズミにとっては十分な通路となるため、見逃しやすいのが実状です。
人目につきにくい場所を移動するから
ネズミは警戒心がとても強く、人間の活動していない時間帯や空間を選んで移動します。天井裏や壁の裏側、床下、配線周り、屋根裏など、ふだん確認が難しい場所を通路として利用するため、建物内でどのルートを移動しているかを特定するのが困難です。加えて、電線や配管を伝って壁や天井などの高所まで移動します。
活動の痕跡に気づきにくいから
ネズミは夜行性であるため、明るい時間帯には目立った行動が見られず、物音やかじり跡、フンなどの痕跡を残しても気づきにくいことがあります。
また、ネズミが通る場所にはラットサインと呼ばれる黒ずんだ擦れ跡や足跡、フンが見られることもありますが、こうした痕跡は目立ちにくい場所に現れることが多く、発見が遅れてしまうことも少なくありません。そのため、気づかないうちに被害が広がってしまうケースもあります。
よくあるネズミの侵入経路
ネズミは建物のさまざまなすき間や構造の隙を利用して屋内に侵入します。侵入経路は建物の外周部だけでなく、屋根や床下、配管まわりなど見落とされやすい場所に存在することもあります。
この章では、特に侵入が多いとされる代表的な経路を詳しく紹介します。
給気口や通気口、配管周辺
壁面に設けられている給気口や通気口は、開口部であるためネズミの侵入口になりやすい箇所です。特に格子の破損や網目が粗い状態になっている場合はクマネズミやハツカネズミが侵入しやすく、給排水管やガス管、電線などが壁を貫通している部分も重点的に確認すべき場所といえます。
屋根のすき間や軒下
ネズミは、屋根周辺の高所からも侵入します。屋根瓦の浮きや軒先との境目、垂木と外壁の間のすき間などは人の目が届きにくく、ネズミにとっては格好の侵入口です。
特に電線や雨樋、給気ダクトなどを伝って屋根まで上がるルートがある場合、ネズミの進入を許しやすい構造になっている可能性があります。
床下換気口や基礎のすき間

建物の基礎に設けられた床下換気口やそのまわりのすき間も、ネズミの侵入経路として多く確認される箇所です。古い建物では通気口の格子が破損していたり、地盤の影響で基礎や土台部分に亀裂が生じていたりすることがあり、そこからネズミが内部へ入り込むケースもみられます。湿気対策のための換気機能を損なわないように配慮しながら、目の細かい金網などで塞ぐ対策が求められます。
排水管周辺
浴室やキッチン、トイレなどの排水管が建物を貫通している部分も、侵入経路として見落とせない場所です。
特に外壁との間にパテやモルタルが適切に充填されていない場合や、劣化して穴が開いてしまっている場合はネズミが入り込む可能性があります。また、ドブネズミは地中の排水ルートや下水溝を通って建物の内部へ侵入してくることがあるため、地面と接している箇所ほど注意が必要です。
侵入経路はネズミの種類によって違う?
ネズミの種類によって、好む侵入ルートや行動範囲が異なります。
例えば、クマネズミは高所を好み、壁のなかや天井裏、屋根裏などの高い場所を移動します。一方、ドブネズミは地上や地下を移動し、下水管や建物の低層部分を通って侵入します。ハツカネズミはほかの種類に比べて小型で、わずかなすき間からも侵入できるため、換気口や配管まわりは特に注意が必要です。
ネズミの侵入経路を特定する方法
ネズミを見かけたり物音がしたりしても、侵入経路が特定できなければ適切な対策を取ることはできません。侵入口が開いたままになっていると、駆除しても再び侵入されてしまう可能性があります。
ネズミの行動を知るうえで手がかりとなるのが、ラットサインです。ラットサインとはネズミが活動した痕跡のことで、代表的なものにフン、足跡、かじり跡、体がこすれた黒ずみ、鳴き声や物音があります。特に体の汚れと脂が壁や配管に付着してできるこすり跡はクマネズミが頻繁に通るルートに現れやすく、侵入経路や移動経路を推測するうえで参考になります。こうしたラットサインは壁の角、家具の裏、天井のふちなど人目につかない場所に残されやすい傾向があります。
さらに、家全体をくまなくチェックすることも欠かせません。屋根裏や床下、通気口、配管の貫通部分、屋根のすき間などを確認し、1〜1.5cm程度でもすき間がないかを注意深く調べることが重要です。
また、小麦粉やベビーパウダーなどをネズミが出入りしていると思われる場所に薄く撒いておくと、通過した際に足跡や体の跡が残るため、目視ではわからなかったルートを可視化できます。こうした調査は、ネズミの行動パターンや侵入経路を把握するうえで有効です。
侵入経路がわからないときの対処法
この章では、侵入経路がわからないときに注意すべきリスクと、適切な対処法について解説します。
侵入経路がわからないまま放置する危険性
ネズミの侵入経路を特定できずに放置すると、被害が長期化・深刻化する可能性があります。ネズミは繁殖力が高く、短期間で個体数を増やして糞尿による衛生被害、イエダニの発生、配線や建材のかじりによる火災リスクなど、多方面に影響が広がるおそれがあります。
再び被害が再発することを防ぐためにも、侵入経路の発見と封鎖は重要です。
害獣駆除を行っている業者に相談する

自力で侵入経路を特定できない場合は、害獣駆除を行っている業者に相談することが効果的です。駆除業者はラットサインや建物構造に精通しており、外部からは見えにくい侵入経路も特定することができます。また、再侵入を防ぐための封鎖工事や環境改善の提案も行ってくれるため、根本的な解決につながります。
特に、ペストコントロール協会に加盟しているような業者であれば、調査から施工、効果確認まで体系的に対応できる体制が整っており、知識や技術面でも信頼して任せることができるといえます。
■侵入経路の特定と駆除は害獣駆除業者に相談を
ネズミの被害を根本的に解決するためには、駆除に加えて侵入経路の封鎖も重要です。ただし、ネズミはわずかなすき間からでも出入りし、人目につかない場所で活動するため、被害の全容を把握するのは容易ではありません。
また、ラットサインの見落としや誤った判断によって、対策が後手に回ると被害が拡大してしまうおそれもあります。再侵入や繁殖のリスクを抑えるためにも、専門知識と経験を持つ害獣駆除業者に相談することが効果的です。
自力で対応が難しいと感じたら、被害を最小限に抑えるためにも、早めにプロの手を借りることを検討しましょう。
アサンテでは、住まいに潜むネズミをはじめとする害獣や害虫の調査・駆除・再発防止までを一貫して対応しています。
1. 調査段階から侵入経路の徹底分析を実施
2. 侵入防止のための封鎖処理や、防鼠資材を活用した施工
3. 衛生環境の改善提案まで総合的に対応
4. ネズミの種類に応じた対策が可能
5. ハクビシン、アライグマ、シロアリ、蜂などの害獣・害虫にも対応
大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。