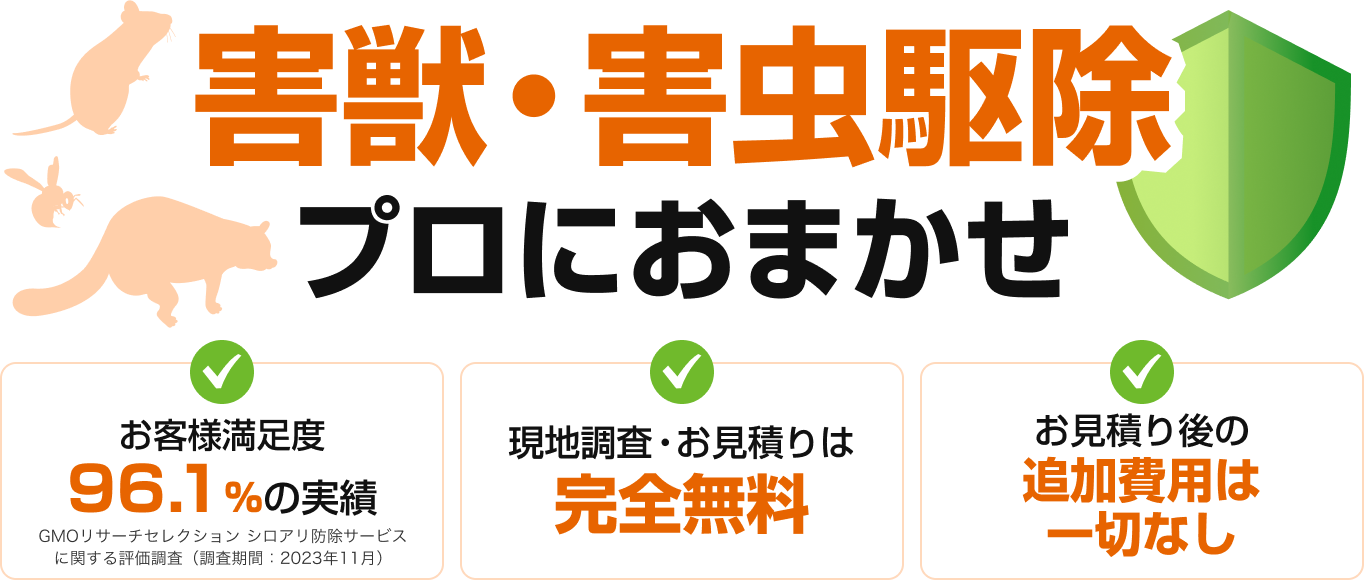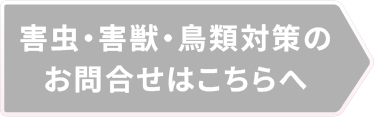ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ネズミ > ネズミの捕まえ方|知っておくべきことやトラップの特徴、自分で捕まえるリスクとは
ネズミの捕まえ方|知っておくべきことや
トラップの特徴、自分で捕まえるリスクとは

住宅におけるネズミ被害は珍しいものではなく、屋根裏や壁から音がする、食品がかじられているなど、日常生活のなかでネズミ被害に気付くことがあります。
この記事では、ネズミの基本的な知識や捕まえ方、捕獲に使えるトラップの種類、自力での対処に潜むリスク、そして業者に依頼する際のポイントまで、順を追って解説します。
目次
ネズミを捕まえる前に知っておくべき3つのこと
ネズミを自力で捕まえることを考えたとき、まず理解しておきたいのはネズミの種類や行動パターンといった基本的な知識です。こういった知識がない状態で捕獲を試みても、失敗したりかえって被害を拡大させたりすることがあります。
この章では、ネズミの基本情報として知っておくべき3つのことを解説します。
ネズミの種類や行動パターンを知る

家庭に被害を与えやすいネズミは主に3種類で、それぞれ特徴や好む環境が異なります。
| 種類 | 特徴 | 主な侵入経路・生息場所 | 警戒心 | 被害の例 |
|---|---|---|---|---|
| クマネズミ | 細身でしっぽが長い | 天井裏、配線周辺、高所 | 強い | 配線をかじる、天井を走る音 |
| ドブネズミ | 大型で力が強い | 床下、水回り、下水周辺 | やや強め | 台所の食材を荒らす |
| ハツカネズミ | 小柄で壁や家具の隙間にも侵入できる | 壁の隙間、引き出し、台所周辺 | 弱め | 食品をかじる、繁殖スピードが早い |
このように、それぞれの習性を理解することで、トラップの設置場所や対策の精度を高めることができます。
「ラットサイン」について知る
ネズミが家のなかにいるかどうかを判断するためには、ラットサインと呼ばれるネズミの活動の痕跡に注目することが重要です。ラットサインには、フンや尿、かじられた痕、黒ずんだ壁の跡などが含まれます。
なかでもフンは見つけやすく、ネズミの種類や行動範囲を推測するための重要な手がかりになります。フンの大きさや形状は種類によって異なり、種類を見分けるヒントにもなるのでフンの特徴を比較してみましょう。
| 種類 | フンの大きさ | 形状 | 色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クマネズミ | 約6〜10mm | 両端が尖った細長い楕円形 | 黒〜濃い茶色 | 天井裏、梁、配線周りなど高い場所で見つかりやすい |
| ドブネズミ | 約18〜20mm | 太くてやや丸みがある(バナナ状) | 黒〜茶褐色 | 床下、倉庫、下水周辺などの地面付近にまとめて排泄する |
| ハツカネズミ | 約3〜6mm | 小さくて細い、米粒状 | 黒〜灰色 | キッチン、食品棚、壁のすき間など低い位置にバラバラに排泄する |
このように、フンの特徴を観察することで、ネズミの種類や行動場所を推定し、適切なトラップの種類や設置位置を判断する材料にすることができます。ラットサインを見落とさず、正確に読み取ることが効果的な駆除の第一歩といえるでしょう。
ネズミのリスクや危険性について知る
ネズミは、配線をかじることで火災の原因になったり、断熱材を巣作りに使用して室内の快適性を損なったりするなど、建物や生活環境に被害をもたらすことがあります。
また、サルモネラ菌やハンタウイルスといった病原菌を媒介することがあり、感染症のリスクがあります。食料品をかじられたり袋を破られたりすると、汚染された可能性を考え処分する必要があるでしょう。
さらに、ネズミは一般的に繁殖力が高く、短期間で個体数が増えて被害が拡大するおそれもあります。
このようなリスクを理解し、ネズミに関する正しい知識を持ったうえで対処しましょう。
【種類別】ネズミ捕獲トラップの特徴と使い方
ネズミを自力で捕獲したい場合、状況に合ったトラップを選ぶことが重要です。ネズミの種類や出没場所、被害の程度によって適した方法が異なるため、それぞれの特徴を把握して使い分ける必要があります。
この章では、一般家庭でも使用される代表的なトラップの種類と使い方を解説します。
粘着シート

粘着シートは、市販されているネズミ捕獲トラップのなかでも入手しやすく使い方が簡単です。ネズミの通り道に設置して、粘着面に足を取らせて動きを封じる仕組みです。
薬剤を使わず、設置直後から効果を期待できる点もメリットのひとつです。ただし、設置場所を誤ると効果が出にくく、ネズミに避けられてしまうこともあります。また、捕獲後は捕まえたネズミを自分で処理する必要がある点、定期的な交換が必要な点には注意が必要です。
捕獲カゴ
捕獲カゴは、ネズミを生け捕りにするためのトラップです。エサでネズミをおびき寄せて内部に入らせた後、自動で扉が閉じて閉じ込める仕組みです。
繰り返し使用できる点がメリットです。ただし、クマネズミのように警戒心の強い種類には効果が出にくい傾向があり、うまく誘導できないこともあります。また、捕獲後に生きている個体への対応を自分で行わなければならず、処理方法や衛生面の対策も考慮する必要があります。
殺鼠剤(毒餌)
殺鼠剤は、有効成分(ワルファリンなどの抗凝血薬)を含むエサをネズミに摂取させて駆除する方法です。
一方で、強い成分を含むため、誤ってペットや小さな子どもが触れてしまうリスクがある点に注意が必要です。また、薬剤を食べたネズミが屋内で死んでしまった場合、発見が遅れると悪臭や衛生面の問題が発生します。設置や保管の際は、使用上の注意をよく読み、適切に管理することが求められます。
バネ式や落とし穴タイプ
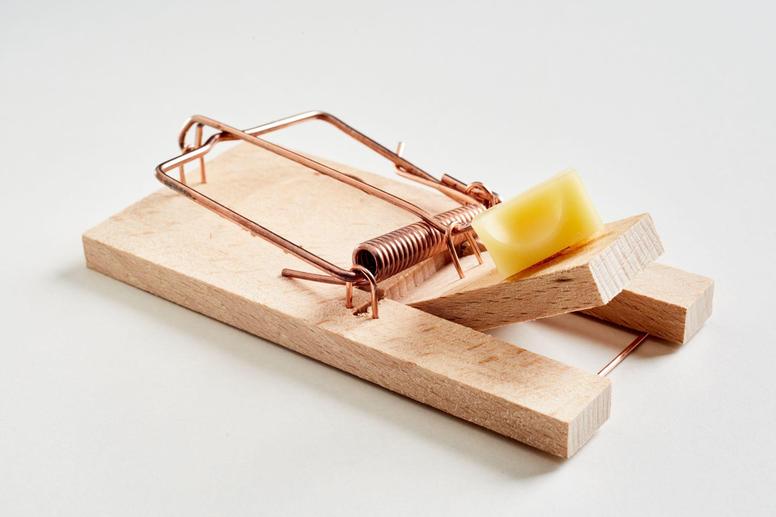
バネ式トラップや落とし穴タイプは、ネズミを瞬時に捕らえる仕組みを持った物理的な捕獲器具です。バネ式は、仕かけられたレバーにネズミが触れると、強い力で押さえ込んで動きを止める構造です。落とし穴タイプはネズミが中に入った瞬間に扉が閉じて脱出できなくなる仕組みで、物理的に閉じ込めて捕獲します。
ネズミを自分で捕まえるリスクや懸念点
市販のトラップを使ってネズミを捕まえる場合、いくつかのリスクや懸念点、注意すべきポイントがあります。
まず、基本的な知識を持っているとしてもネズミの捕獲は難しく、より専門的な知識や対処が求められることが少なくないという点です。クマネズミのように警戒心が強い種類は、人の気配やトラップに対して敏感に反応し、なかなか近づこうとしません。また、行動範囲が複雑で特定しにくいため、適切な位置にトラップを設置できないケースもあります。
加えて、捕獲に成功したとしても生きたネズミや死骸の処分は多くの方にとって簡単なことではないでしょう。不適切な処理によって感染症にかかってしまうリスクも考慮する必要があります。
さらに、根本的な解決のためには巣や侵入口を特定して対策を施すなど再侵入を防ぐための対処が必要です。繁殖力の高いネズミに対して部分的な対応を続けることは、被害を長引かせる原因にもなりかねません。
このように、自力でネズミを捕まえる場合、費用を抑えられる可能性がある一方で、リスクや限界があることを理解しておくことが大切です。特に、再発防止や衛生管理を含めた根本的な対策を講じるには、専門的な視点に基づいた対応が欠かせません。
ネズミ被害は業者に依頼すべき理由
この章では、業者にネズミ駆除を任せることの具体的なメリットを紹介します。
根本的な駆除や対策が可能
ネズミの駆除には、単に目の前の個体を捕らえるだけでなく、被害の原因となる侵入口の封鎖や巣の除去といった根本的な対策が必要です。駆除業者は被害の範囲やネズミの種類を的確に調査したうえで、再発防止を含めた包括的な対応を行います。
特に、ペストコントロール協会に加盟している業者であれば、一定の技術基準や法令遵守を前提とした信頼性の高いサービスが提供されていると考えることができます。住環境全体の衛生管理やリスク低減まで視野に入れた対応が期待できるので、信頼できる依頼先を選定したい場合は加盟業者を探してみましょう。
死骸の処理や清掃を任せられる
捕獲した際のネズミや死骸、フン・尿などによる汚れの処理は、想像以上に大きな負担です。死骸の放置は悪臭や細菌の繁殖につながるので、自力での処理に不安がある場合は駆除業者に任せることを検討するとよいでしょう。
業者に依頼することで、こうした処理をすべて任せることができます。専用の防護具や薬剤を使った作業により、見えにくい部分まで丁寧に対応してもらえる点もメリットです。特に感染症や害虫の二次被害を防ぐうえで有効です。
■ネズミを捕まえたい場合は業者へ依頼しよう
自力でのネズミ捕獲にはリスクや限界があります。再発防止や衛生管理を含めた根本対策を求めるなら、業者による体系的な対応が効果的です。早めの相談が解決への第一歩となるため、ネズミを見かけたら早めに駆除業者へ相談しましょう。
アサンテでは、現地調査から開始し、ネズミの生息状況を確認したうえで適切な駆除・防鼠提案を行っています。
1. 徹底した調査を実施
2. 自社施工で迅速・丁寧な対応
3. ネズミだけでなく、アライグマやハクビシンなどの害獣にも対応
4. 駆除後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全
5. ペストコントロール協会加盟
大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。