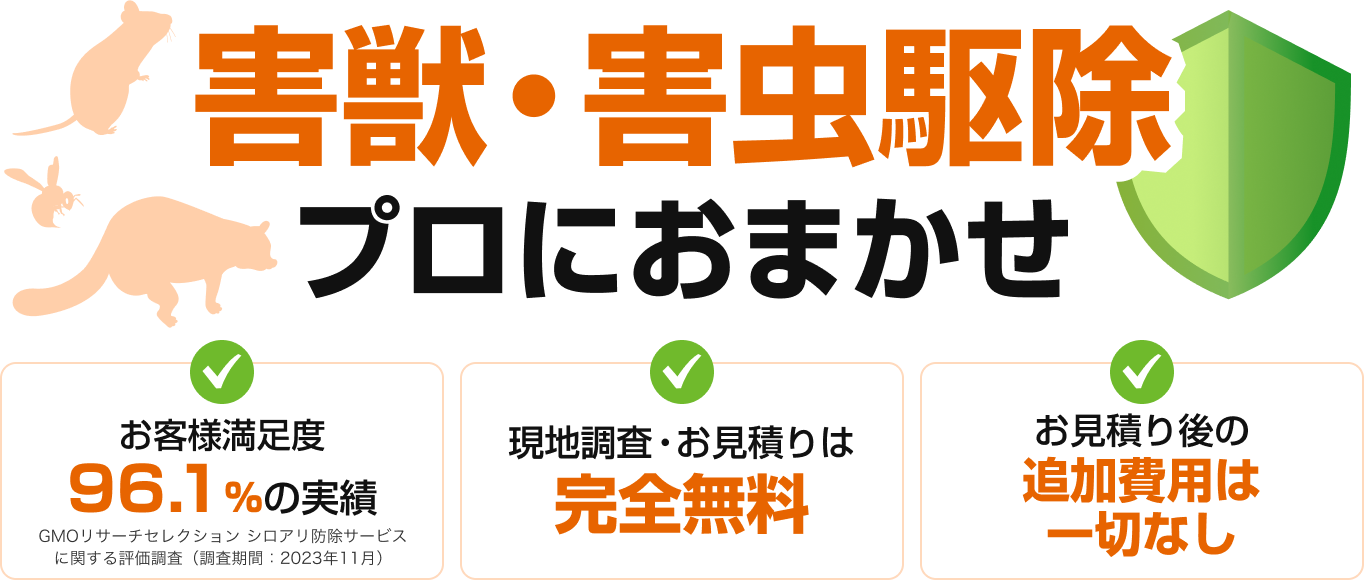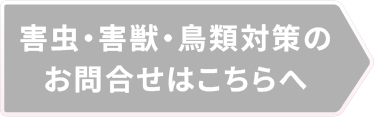ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ネズミ > クマネズミの駆除が難しい理由を解説!侵入経路や被害、プロに依頼するメリットとは
クマネズミの駆除が難しい理由を解説!
侵入経路や被害、プロに依頼するメリットとは

配線をかじったり、病原菌を媒介したりすることでさまざまなトラブルを引き起こすネズミ被害ですが、ネズミのなかでもクマネズミは賢くて警戒心が強いため、駆除が難しいといわれています。
本記事では、クマネズミの生態や侵入経路、被害の実態、自力での駆除が難しい理由を詳しく解説します。
クマネズミの特徴
クマネズミは、日本の住宅やビルに多く出没する代表的な害獣のひとつです。まず最初に、クマネズミの外見的な特徴や習性を解説します。
見た目

クマネズミは体長18〜24cmほどで、尾長は20〜27cmと尾が体よりも長い個体が多く見られます。毛色は灰褐色〜黒褐色で、ほかのネズミに比べてスリムな体形に対し耳や目が大きく、ドブネズミなどより小柄な印象を受けやすいのが特徴です。尾の長さや体形の違いから、見た目だけで種類の判別が可能な場合もありますが、確実な判定には専門的な知識が必要です。
ドブネズミとの違い
クマネズミとドブネズミは、行動範囲や警戒心の強さに大きな違いがあります。
クマネズミは高所が得意で壁づたいに移動するなど行動が広範囲に及び、屋内のさまざまな場所に現れます。一方ドブネズミは、地下や下水まわりなど低所に現れる傾向があり、水回りや地面の近くを中心に活動するのが特徴です。
また、クマネズミはとても警戒心が強く神経質で、新しいものを避ける傾向があります。それに対してドブネズミは比較的大胆で、仕掛けた罠にもかかりやすいとされています。
このように、クマネズミはドブネズミに比べて行動範囲が広く用心深いため、駆除が難航しやすいといえます。
寒さに弱い
クマネズミは寒さに弱いため、気温が下がると屋内に侵入し、暖かい天井裏や壁の中に入り込んで巣を作ろうとします。特に暖房の効いた室内はクマネズミにとっても快適な環境で、冬季に活動が確認されるケースが増える傾向があります。
ドブネズミと比べると寒さへの耐性が低く、家屋内への侵入が被害拡大の主な原因となることが少なくありません。
垂直移動が得意で高い場所に移動できる
クマネズミの大きな特徴のひとつが、垂直方向の移動能力が高い点です。配管や電線、壁の凹凸などを伝って建物の高所まで移動することが可能で、屋根裏や上層階への侵入がよく見られます。
そのため、1階で姿を見かけなくても2階や天井裏に潜んでいることがあり、発見や対処が遅れやすい点には注意が必要です。
クマネズミの主な侵入経路
クマネズミは、わずかな隙間からでも建物内に侵入してきます。特に多いのが屋根や軒下、換気口や通気孔など、外とつながる開口部です。
また、配管や電線を伝って高所に移動し、屋根裏から侵入するケースが確認されており、エアコンスリーブや通風口の網の破れなど、人の目では見落としがちな場所が入口になっている例もあります。見た目に異常がなくても被害が進行している場合があり、侵入に気づきにくいのもクマネズミの厄介な点です。
そのため、日ごろから建物の状態を確認し、異常があれば早めに対策を講じることが被害の拡大を防ぐポイントです。
クマネズミによる被害
クマネズミを放置すれば、住まいや生活全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、具体的にどのような被害があるのかを項目ごとに紹介します。
家屋や配線などの設備を壊す
クマネズミは柱や壁、断熱材などをかじって巣を作るため、建物の劣化が進みます。なかでも、特に問題なのが配線の被害です。家電やネット機器のコードがかじられると、停電や通信障害、さらに火災の原因にもなります。
病原菌やダニを媒介する
クマネズミは、糞尿や体毛などに付いた病原菌を拡散する可能性があります。代表的なものとしてサルモネラ菌やレプトスピラ症などがあり、人に感染すると重症化することもあるため、注意が必要です。
また、クマネズミに寄生しているダニやノミが原因で、皮膚炎やアレルギーを引き起こす例もあります。キッチンや食器棚に出没した場合は、食品や食器を介した二次感染のおそれがあるため、衛生面でも油断できません。
騒音被害と精神的ストレス
天井裏や壁の中から聞こえる足音やガサガサという物音は、クマネズミの活動音である可能性があります。こうした音が夜間に続くと、睡眠の質が下がり、心理的なストレスになってしまいます。
食材への被害
クマネズミは嗅覚が鋭く、食品やペットフードの保管場所を狙って侵入してきます。袋を破って中身を食べるだけでなく、排せつ物などで食器棚やキッチン周りを汚染することで、食材が使えなくなる事態も起こります。
特に飲食物を扱う店舗では、ネズミによる食害が異物混入として扱われるなど、営業停止や風評被害につながるリスクを重く考えなければなりません。
クマネズミの駆除が難しい理由
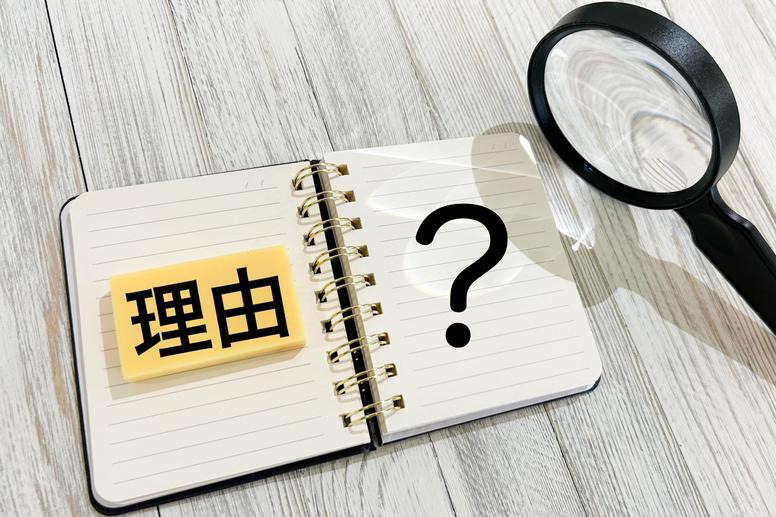
ここからは、クマネズミ駆除を困難にしている4つの要因を紹介します。
クマネズミに合う対策を行う必要がある
クマネズミはほかのネズミと行動の特性が異なるため、クマネズミを対象にした適切な方法でなければ駆除が思うように進みません。例えば、ドブネズミ向けに設置された開放型の罠では、警戒心の強いクマネズミに見破られてしまうこともあります。
そのため、糞の形や足跡、行動パターンなどからどの種類なのかを見極めることが大切で、クマネズミに合う対策を行わなければ、効果が出ないまま被害が拡大・長期化するおそれがあります。
巣の場所を特定するのが難しい
クマネズミは屋根裏や壁の中など、人の目が届きにくい場所に巣を作るため目視での確認が困難で、巣の位置を特定しにくいことが大きな障壁となります。適切な対処をするには、音や糞の位置、天井裏の状況などからクマネズミの活動範囲を絞り込む必要があります。
警戒心が強く神経質
クマネズミはとても用心深く、新しいものや変化に対して強い警戒心を示します。この性質はネオフォビアと呼ばれ、毒餌やトラップを回避する要因となります。また、仲間が死んだ場所や原因を学習し、同じ場所や方法ではトラップを回避するという集団学習の傾向もあります。
クマネズミの学習能力の高さが、駆除の成功率を下げる一因になっているのです。
侵入経路への対策、整理整頓が不十分
クマネズミは配管やわずかな隙間を通じて侵入するため、完全に遮断するには丁寧な点検と対策が求められます。
さらに、段ボールやペットフードなどの放置は巣材や餌を与える原因となり、再侵入を助長してしまいます。駆除を徹底するには、侵入口の封鎖だけでなく、室内環境の整理・清掃も並行して行う必要があります。
このような対策を自力ですべて行うことは難しいため、クマネズミの侵入・再発が防ぎきれず被害を繰り返しやすくなってしまいます。
被害が広がる前にプロに依頼するのがおすすめな理由

クマネズミの駆除は難易度が高く、自力で対応するには限界があります。被害の再発や長期化を防ぐためにも、専門業者への依頼を早めに検討することがおすすめです。ここでは、プロに依頼するメリットや、業者選びのポイントを紹介します。
プロのクマネズミ駆除のメリット
ネズミ駆除を請け負っているプロは、まず事前調査から種の判別、生息状況の確認までを丁寧に行い、状況に合った対策を立てます。粘着シートや毒餌、捕獲機の使い分けや、侵入口の封鎖・防鼠施工まで一貫して対応してもらえます。
また、再発リスクの高い場所を特定し、環境改善を含めた予防策も提案してくれるため、駆除効果の持続が期待できます。
クマネズミ駆除の業者選びのポイント
クマネズミは駆除が難しいため、クマネズミの対応実績があるかを事前に確認する必要があります。特にペストコントロール協会に所属している業者は、ネズミの生態や行動パターンへの理解が深く、再発防止策まで考慮した対応を行ってもらえるでしょう。
■クマネズミ駆除はプロに相談するのがおすすめ
クマネズミは、警戒心の強さや高所への移動能力といった特性から、一般的な駆除ではなかなか対処しきれません。
被害を放置すれば、家屋の損傷や健康被害、精神的ストレスのリスクが増大してしまうので、被害に気づいたら早めにプロの業者に相談することが重要です。
アサンテでは、現地調査から駆除、再発防止までを一貫して対応しています。建物の構造や被害の状況に合わせ、クマネズミに合う対策をご提案し、丁寧に処置を進めていきます。
徹底した現地調査で原因を見極め
侵入口の封鎖や環境整備にも対応
専用機器を使い、生息域や通路を把握して駆除
アライグマ、ハクビシンなどほかの害獣にも対応
作業後の片づけや清掃までしっかり対応
大切な住まいを長く守るためにも、ネズミ被害が広がる前にアサンテの害獣対策をご検討ください。