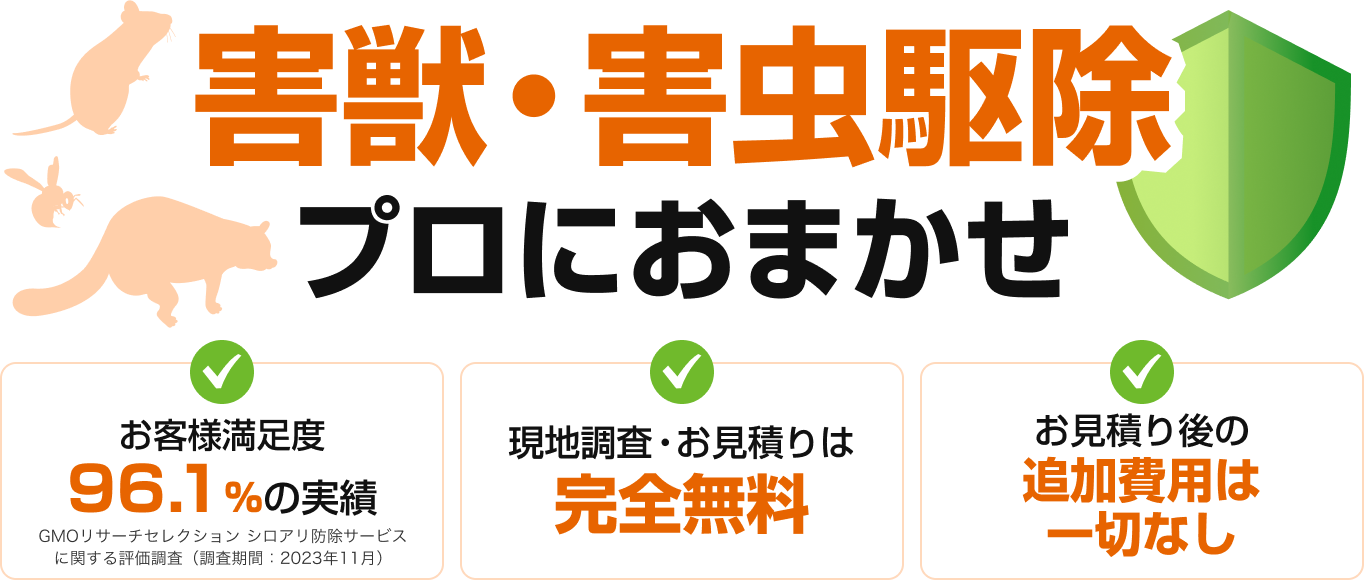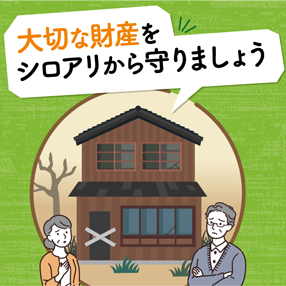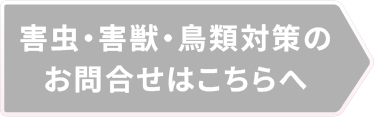ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマの天敵は日本にいない?引き起こされる被害や対策のポイントとは
アライグマの天敵は日本にいない?
引き起こされる被害や対策のポイントとは

屋根裏から物音がしたり、畑の作物が荒らされたりした原因としてアライグマの可能性を疑い、調べている方もいるでしょう。アライグマについて調べるなかで、「アライグマには天敵がいる?」と疑問に感じたことはありませんか?
本記事では、アライグマの天敵やアライグマによる被害が広がる理由、見かけた際の対処法を解説します。
アライグマの天敵は日本にいない?
アライグマは日本各地で生息域を広げており、農作物や住宅への被害が深刻化しています。
この章では、アライグマの天敵と、日本でアライグマが定着したことによる影響を解説します。
アライグマの天敵はオオカミやピューマ

アライグマの原産地である北米では、オオカミやピューマなどの大型肉食獣が生息しています。こういった天敵(捕食動物)が身近に存在する環境では、アライグマの個体数は自然と抑えられる傾向にあります。
一方、日本のように大型の捕食動物がいない環境では、アライグマの個体数増加に歯止めがかかりません。ドイツやフランスなどでも日本と同様に天敵がおらず、アライグマの野生化が進んでいると報告されています。
天敵がいない日本でアライグマが定着したことによる問題点
日本にはアライグマの天敵となる動物が存在せず、個体数が増える条件が揃っています。その結果、農村部から都市部へと生息域が拡大し、住宅への侵入や農作物への被害、感染症の媒介といった問題点が懸念されています。
日本の農地は、アライグマにとって栄養価が高くサイズも大きい作物を短時間で効率よく摂取できる餌場です。手間をかけずに食料を確保できる環境がアライグマの定着や繁殖を支える要因となり、被害の拡大につながっていると考えられています。
天敵のいないアライグマが引き起こす3つの被害
天敵のいない環境で増えたアライグマは、人の生活圏に生息域を広げています。それにより、屋根裏や物置に侵入して棲み着く、病原体を媒介するといった被害が懸念されています。
ここでは、アライグマが引き起こす3つの被害について解説します。
家屋への侵入と建物の損壊や汚損
アライグマは木登りや狭い足場の移動が得意で、雨樋や木の枝を伝って屋根に上がることができます。屋根のすき間をこじ開けて屋根裏に侵入し、そのまま棲み着くケースや、床下の通気口や土台部分のすき間から侵入するケースがあります。
特に春先の繁殖期は子育て場所として天井裏が選ばれやすく、断熱材を引きちぎったり、フン尿で内部を汚したりする被害が出やすくなります。騒音や悪臭に加え、天井の修繕や清掃作業に費用がかかるため、できるだけ早く対処することが求められます。
農作物や家庭菜園への食害
アライグマはトウモロコシやスイカ、ブドウ、イチゴなどの甘みの強い作物を好みます。特に熟した果実を狙って食べ荒らす傾向があり、収穫前の農作物に大きな損失を与える可能性があります。例えば環境生活部自然環境局野生動物対策課の調査によると、北海道では2022年度、アライグマによる農作物への被害額が約1億4,400万円に達しました。
参照:北海道公式ホームページ
アライグマは家庭菜園のネットやフェンスを破って侵入し、野菜や果物を荒らすケースもあるため、家庭菜園を楽しんでいる家庭でもアライグマの食害に遭う可能性と無縁ではありません。
人やペットにも危険が及ぶ感染症のリスク
アライグマは野生動物であり、見た目の可愛らしさとは裏腹に多くの病原体を保有している可能性があります。
代表的な感染症として、アライグマ回虫が挙げられます。フンに含まれるアライグマ回虫の卵が人やペットに感染すると、体内で幼虫が移動して視覚障害や神経障害を引き起こします。進行した場合は脳や目の損傷を引き起こすおそれもあります。
また、レプトスピラ症やサルモネラ感染を媒介する可能性もあり、不用意に接触するのは危険です。
人の手によるアライグマ対策のポイント

日本には天敵がいない以上、アライグマの被害を抑えるには人の手による対応が求められます。
この章では、アライグマ対策のポイントを4つ紹介します。
アライグマに関わる法律について知る
アライグマの追い出しや捕獲には、まず各自治体のホームページや環境省の資料を確認し、関連する法律や手続きの流れを把握しておくことが大切です。
アライグマは、鳥獣保護管理法と外来生物法により捕獲や駆除、飼育、運搬などの行為が規制されています。もし許可を得ずに捕獲を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、自治体ごとにアライグマの捕獲や追い出しを行うための申請先、手続きの流れが異なる場合があります。各地域のルールに沿って対応できるよう、事前の確認を忘れないようにしましょう。
被害が出る前、拡大する前に行動する
アライグマによる被害を防ぐには、早期の対応が重要です。アライグマは1回の出産で3〜6頭の子を産むため、放置すると短期間で個体数が増え、被害が一気に広がるおそれがあります。
特に天井裏や床下は、アライグマの侵入に気付きにくい場所です。早めに異変を察知するために、定期的にフンが落ちていないか、においの変化がないかをチェックしたりすることをおすすめします。アライグマの存在を示すサインを見逃さず、初期段階で対応すれば、駆除や修繕にかかる費用や手間を軽減できる可能性があります。
自治体やプロの業者と連携が必要
自治体によっては、アライグマ捕獲のための申請手続きの案内や捕獲器の貸し出しを行っています。しかし、設置や捕獲後の対応は自己責任となる場合が多く、安全面や再発防止策までは十分にカバーできません。
そのため、実際の捕獲や駆除作業は、経験豊富なプロの業者と連携することが効果的です。業者は追い出しや捕獲はもちろん、侵入口の封鎖、清掃などの対応を一括で行えるため、効果的な対策を行える可能性が高まります。
法律による規制や怪我、感染症のリスクなど、アライグマ対策は専門的な知識がないと難しいといえます。必要に応じて自治体の制度を活用しつつ、プロに相談することがおすすめです。
再侵入を防ぐには専門的な対策が必要
アライグマの再侵入を防ぐには、侵入口の封鎖を含む専門的な対策が欠かせません。一度追い出しても、屋根のすき間や通気口など、わずか5cm程度のすき間が残っていれば再び侵入されてしまうおそれがあります。
害獣駆除のプロであれば、侵入口の特定から封鎖作業までを一貫して対応でき、再侵入を防ぎやすくなります。特にペストコントロール協会に加盟している業者は、一定の基準に基づいた対応が期待でき、信頼性も高いといえます。
■天敵に頼るのが難しいアライグマ対策はプロに相談しよう
アライグマは本来、日本に生息していなかった外来生物です。国内にはアライグマの天敵となる動物がおらず、生態系や生活環境に被害をもたらす可能性があります。
屋根裏への侵入や農作物被害、感染症リスクなどその影響は多方面に及び、その繁殖力の高さから短期間で被害が拡大してしまうおそれもあるため、早期の対策が重要です。
安全面や再発防止まで考慮するなら、経験豊富なプロの業者と連携することが効果的です。
アサンテでは、アライグマなどの害獣被害に対し、状況に応じた対応を行っています。
1. 侵入経路や足跡・フンの有無などを丁寧に現地調査
2. アライグマの習性を踏まえた追い出し作業
3. 金網やパネルなどで侵入経路を塞ぎ、再発を防止
4. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全
5. ハクビシン・ネズミ・コウモリなど、ほかの害獣にも対応可能
大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。