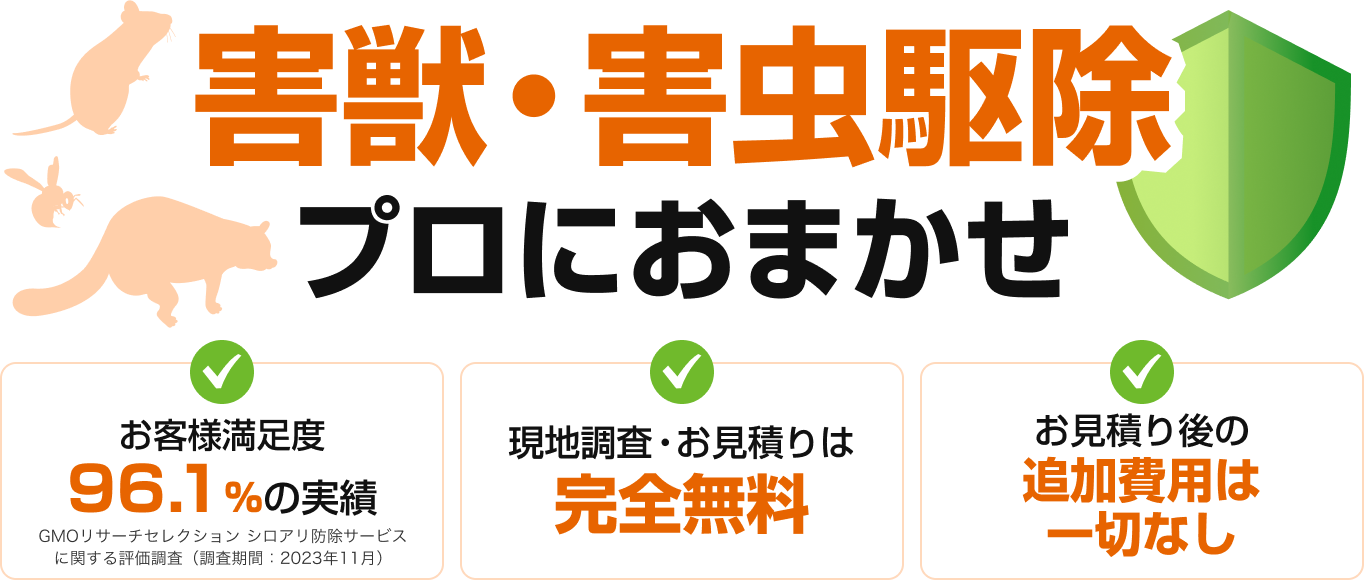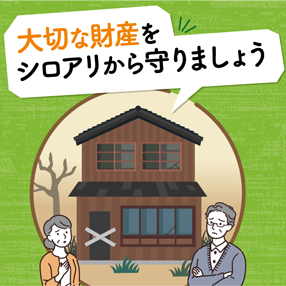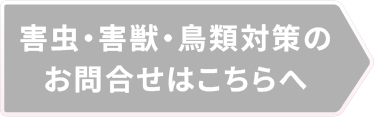ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマの危険性とは?見つけたときの注意点や対処法をわかりやすく解説
アライグマの危険性とは?
見つけたときの注意点や対処法をわかりやすく解説

アライグマはかわいらしい見た目に反して気性が荒く、安易に近づくと噛まれたり引っ掻かれたりするおそれがあります。
さまざまな病原菌を保有しているため、直接的な攻撃だけでなく、糞尿や毛にも注意が必要です。
アライグマによる農作物や住宅への被害も深刻化しており、アライグマの危険性が注目されています。
アライグマを見つけたときに適切に対処できるよう、アライグマの危険性や注意点について詳しく解説します。
アライグマの危険性
日本にはアライグマの天敵がいないため個体数が増えやすく、人や住宅、農作物などに悪影響を及ぼすことがあります。ここでは、アライグマの危険性を5つに分けて解説します。
人への攻撃性
アライグマは基本的には臆病ですが気性が荒く、追い詰められたり巣や子どもを守るために鋭い爪や歯で攻撃してくることがあります。攻撃性が高く、噛まれたり引っ掻かれたりすると重傷を負うこともあるので、見かけても近づかないようにしましょう。
媒介する病気
アライグマは複数の感染症を媒介する可能性があり、噛みつかれたり糞尿を触ったりすると感染するおそれがあります。アライグマが媒介する可能性がある感染症の例は以下のとおりです。
狂犬病
アライグマ回虫症
レプトスピラ症
上記以外にも、アライグマに寄生するマダニやヒゼンダニに刺されると、かゆみや腫れ、水ぶくれなどの症状が現れ、刺されたことが原因でさまざまな病気に感染するおそれがあります。
また、アライグマ回虫症は人の脳や神経に障害を残すこともあるため、糞尿の処理や接触には注意が必要です。
農作物への被害
雑食性のアライグマは、野菜や果物などあらゆるものを口にするため、農作物への被害も拡大しています。
2023年度の農林水産省による調査では、アライグマによる農作物への被害額は約48億円でした。5年前の被害額が約36億円だったことから、被害が拡大しているのがわかります。
アライグマによる被害は、農村地帯だけでなく都市部でも拡大しているため、家庭菜園で野菜や果樹がある場合は必要に応じて対策を検討しましょう。
住宅への被害住宅への被害
アライグマは、10cmほどの隙間から住宅に侵入することができます。特に床下と屋根裏に侵入されるケースが多く、そのまま棲みついてしまうことも少なくありません。
断熱材の破損や汚損、配線や柱をかじる、糞尿による悪臭や木材の腐食など、さまざまな被害が起こる可能性があるので、アライグマが家屋に侵入している可能性がある場合はなるべく早く害獣駆除業者に相談するのがおすすめです。
環境や生態系への影響

アライグマは雑食性で、昆虫や両生類、鳥類の卵、小型哺乳類まで幅広く捕食します。また、手先が器用で木登りも得意なので、樹上に巣穴のあるムササビやフクロウなどを捕食することもあります。
さらに、ニホンザリガニやオオサンショウウオなど希少性の高い在来種も捕食することがあるため、在来種の減少や生態系のバランス崩壊への懸念から特定外来生物に指定されています。
アライグマを見つけたときの注意点や対処法
それでは、アライグマを見つけたときはどうすればよいのでしょうか。アライグマを見つけたときの注意点と対処法について解説します。
安易に近づかない
アライグマは野生動物で、予測不能な行動を取ります。怪我や感染症のリスクを考え、アライグマを見つけても容易に近づかず、距離を保って刺激しないようにしましょう。
餌付けしない
アライグマは知能が高く学習能力があるため、餌付けをすると餌がもらえる場所として覚えてしまい、繰り返しやってくるようになります。人間の生活圏に慣れ、頻繁に出没するようになると農作物や家屋への被害拡大や感染症リスクが高まります。
かわいいからといって、餌を与えるのはやめましょう。
出没箇所の衛生管理を徹底する
アライグマの毛や糞尿には病原菌や寄生虫が含まれている可能性があるため、見つけた場合は直接触れず、手袋やマスクを着用して清掃する必要があります。清掃後は手指の消毒を徹底し、再度やってくる可能性を考慮して、餌となるようなものを撤去するなどしっかり環境を整備しましょう。
アライグマの駆除をプロに依頼すべき理由
アライグマは、外来生物法と鳥獣保護管理法によって管理されています。法律違反や怪我、感染症、再侵入のリスクなどを踏まえ、適切に対処するのは個人では難しいでしょう。
ここからは、法律やアライグマの生態に精通したプロの駆除業者に依頼すべき理由を3つ解説します。
法律に則って対処してもらえる
アライグマの捕獲や飼育、移動には外来生物法と鳥獣保護管理法による法律上の制限があります。無許可での駆除や捕獲は罰則の対象になるため、適切な許可や手続きを踏んで対応することが求められます。
アライグマの駆除を行っている業者なら、法律を順守し、安全性に配慮して対処してもらえます。なお、追い出し作業であれば許可は不要です。
調査から再発防止まで任せられる
害獣対策を行う業者は、侵入経路や被害状況を詳しく調査し、追い出しや駆除の計画を立てます。
侵入経路の封鎖や環境改善、衛生管理などを組み合わせて、再発を防ぐための包括的な対策を実施します。ペストコントロール協会に加盟している業者は、一定の技術基準や法令遵守の体制が整っていると考えられるので、長期的な被害防止を目的とした総合的な対策を提案してもらえるでしょう。
衛生管理や感染症リスクに対応できる
アライグマはさまざまな病原菌を保有しており、糞尿による感染症リスクがあります。プロは防護具や専用の殺虫剤などを用い、適切な方法で処理や清掃をしてくれるので、衛生管理と感染症リスクの低減が期待できます。
アライグマの駆除にかかる平均的な費用相場

一般的な一戸建て住宅の場合、追い出しや捕獲作業、侵入経路の封鎖、清掃まで含めると平均的な費用相場は5〜30万円です。被害が軽度で、追い出しのみで対応できるケースでは費用を抑えられる傾向がありますが、天井裏に巣を作られている場合や、複数頭の捕獲が必要な場合は20万円以上の費用がかかるケースが多いでしょう。
※2025年8月時点のインターネット等の公開情報をもとにしています。
費用には以下のような項目が含まれるのが一般的です。
捕獲または追い出し作業:罠や忌避剤の設置・回収、捕獲後の処理
侵入経路の封鎖工事:屋根や壁、床下の穴や隙間の封鎖
糞尿や残骸の清掃:糞尿や残骸の除去、殺虫など
費用は、被害の状況や建物の構造、作業内容によって変動します。複数業者から相見積もりを取り、作業内容と費用のバランスを確認しましょう。
■アライグマ被害は危険性にも対処できるプロに相談を
アライグマは、攻撃性の高さや感染症リスクなど、さまざまな危険性をもつ動物です。また、雑食性のアライグマによる農作物への被害は深刻で、農村地帯だけでなく都市部にまで被害が拡大しています。
しかし、アライグマ対策を行うには法律や安全面のリスクから難易度が高く、個人で行うには限界があります。
被害が広がる前に、調査から駆除、侵入経路封鎖、清掃まで一貫対応できるプロの業者に相談するのがおすすめです。
アサンテでは、無料の事前調査や見積り作成、アフターフォローなど、納得してご依頼いただける体制を整えています。
1. 信頼と実績の東証プライム上場企業
2. 害獣対策のプロによる自社施工
3. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全
4. 害獣の対策やご相談、調査は最短即日で対応
5. アライグマ以外の害獣・害虫も対応
大切な家を守るために、アサンテの害獣対策をご検討ください。