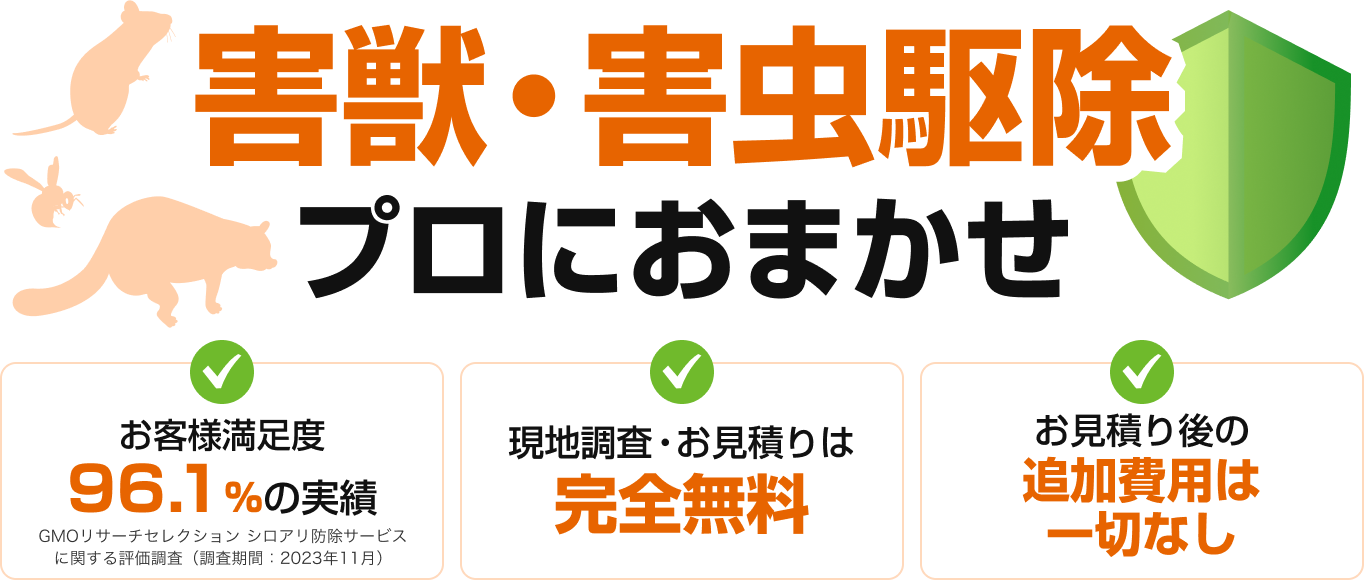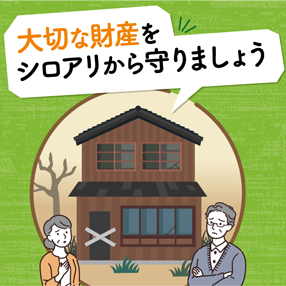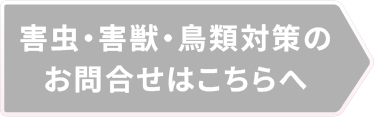ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマに毒餌を使用しても大丈夫?法律違反になる可能性やリスクとは
アライグマに毒餌を使用しても大丈夫?
法律違反になる可能性やリスクとは

アライグマの被害は、タヌキやハクビシンによる被害と並んで問題視されています。
アライグマの追い出しや捕獲は専門的な知識がないと難しいですが、捕獲器で捕まえたり毒餌を使用して駆除したりしようと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、アライグマの捕獲や駆除は法律違反にあたる可能性があり、注意が必要です。
この記事では、アライグマに毒餌を使用する際の注意点を詳しく解説します。
アライグマによる被害
農林水産省の調査によると、アライグマによる農作物被害は2016年には3億3千万円を超えています。2006年度は1億6千万円程度だったので、アライグマによる農作物への被害額は10年間で約2倍になっています。
主な被害は野菜類が約2億円で1位、次いで果樹が約1億円で、被害全体の90%以上を占めています。
これほどまでに被害が増加した原因として、アライグマの捕獲が増殖のスピードに追い付いていないことが理由に挙げられます。2010年に24,810匹だった捕獲数は2015年に37,394匹と約1.5倍に増加していますが、それ以上にアライグマの増殖スピードが早いのが現状です。
また、捕獲時にハクビシンやタヌキ、アナグマなど別の動物が罠にかかってしまうこともあり、アライグマを狙って捕獲するのは難しい傾向にあります。そのため、アライグマ専用の捕獲機の開発も進められています。
アライグマに毒餌を使用しても大丈夫?

日本ではアライグマは外来生物法や鳥獣保護管理法の規制対象であり、駆除方法や捕獲の可否は法律で定められています。また、毒餌の使用は基本的に禁止されており、限られた条件下でのみ使用許可を受けることができます。
まずはアライグマや毒餌に関する法律についてしっかり知っておきましょう。
アライグマ駆除に関係する法律
アライグマ駆除に関係する法律は次の2つです。
外来生物法
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
外来生物法とは、輸入などで海外から入ってきた生物で日本での生態系や農林水産物へ被害を与える生物、または被害を与える可能性がある生物に対して定められた法律です。
アライグマは特定外来生物に指定されており、飼育や譲渡、捕獲後に逃がすことが禁止されています。
また、アライグマは外来生物法だけでなく鳥獣保護管理法によってルールが定められています。
鳥獣保護管理法とは、鳥獣の保護と管理、狩猟の適正化を図るための法律です。野生動物の狩猟や捕獲はこの法律によって保護・管理されていますが、その動物による生活環境や農林水産業、生態系への被害などを考慮し、被害対策の一つとして法定猟法による捕獲などが許可されることがあります。
鳥獣保護管理法によっても保護されているアライグマの捕獲や駆除のためには、原則として市町村への許可申請が必要です。
法律違反による罰則や行政指導の可能性
毒餌を使用する行為は、鳥獣保護管理法の第36条にある危険猟法に該当します。危険猟法は、限られた条件下で第37条の規定に基づき許可を得た場合のみ使用できます。
この規定に違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、狩猟免許の効力停止や取り消しといった行政指導が行われる可能性もあります。
誤飲による被害のリスク
毒餌を食べる可能性があるのはアライグマだけではありません。
設置する場所にもよりますが、飼い犬や飼い猫、子どもが誤って口にしてしまうリスクがあります。ハクビシンやアナグマなど、アライグマ以外の動物が食べてしまうこともあります。
毒餌は、狙った対象以外を巻き込んでしまうリスクがある方法だといえます。
死骸処理など衛生面でのリスク
アライグマが毒餌によって死亡した場合、その死骸は捕獲者が鳥獣保護管理法に基づき責任を持って処分しなければなりません。
アライグマの死骸は、放置すると悪臭や害虫発生の原因になります。さらに、アライグマは病原菌や寄生虫を保有している可能性があるので、適切な防護具を着用し、衛生的に処理することが求められます。
毒餌以外のアライグマ対策の方法
毒餌の使用は法律や安全面のリスクが高く、一般の方が使用するのは現実的ではありません。では、ほかにどのような方法があるのでしょうか。ここでは毒餌以外のアライグマ対策を解説します。
許可を得て罠を使用して捕獲する

アライグマの捕獲のために自治体に申請し、許可を得て箱罠などの捕獲器を使用してアライグマを捕獲する方法があります。箱罠を持っていない場合でも、自治体に申請すれば貸し出してもらえる可能性があります。
なお、箱罠はハクビシンやタヌキなどが罠にかかってしまう錯誤捕獲を防ぐため、手を箱罠の上部から奥深くまで差し込むことができるアライグマ特有の動作に対応した捕獲器の使用を検討しましょう。
忌避剤などを使用して追い出す
アライグマは嗅覚が鋭く匂いに敏感です。そのため、刺激臭など匂いを活用した忌避剤を使用して追い出すことが可能です。忌避剤には市販されているものや、木酢液のように自作できるものもあり、家屋や物置の天井裏などをねぐらにされている際に有効な手段です。
アライグマに忌避剤は有効ですが、匂いの効果が切れないよう定期的に交換が必要です。また、匂い慣れしてしまうと効果が薄れてしまうケースもあるので、同じ忌避剤を使い続けるのではなく、定期的に忌避剤の種類を変えるのも有効です。
侵入口を封鎖する
屋根裏や床下など、アライグマの侵入経路がわかっている場合は侵入口を封鎖しましょう。
外壁に小さな人の手のような跡を見つけた場合、近くにアライグマの侵入口がある可能性が考えられます。アライグマはわずか10cmほどの隙間でも侵入でき、身体能力も高く、垂直にも水平にも1m以上ジャンプできるといわれています。意外な場所が侵入口になっていることもあるので、出入りできそうな小さな隙間がないかよく確認しましょう。
侵入口を封鎖する場合には、以下の点に注意が必要です。
金属の網や硬い木材など頑丈な材料を使用する
アライグマが中にいる状態で封鎖しない
アライグマは手先が器用で力も強いため、簡易な封鎖ではこじ開けてしまう可能性があります。金網や硬い木材でしっかり塞ぐのがポイントです。
封鎖作業を行う際は、アライグマを中に閉じ込めてしまわないよう、行動パターンをよく確認して外に出ているタイミングで行いましょう。
害獣駆除のプロに相談する
法律遵守や安全性を確保しながらアライグマ対策を行うためには、法律やアライグマに関する専門知識と経験が必要で、個人で対応するのは難しいといえます。
アライグマによる被害をできるだけ抑えるためにも、害獣駆除のプロに相談するのがおすすめです。
害獣駆除のプロであれば調査、捕獲または追い出し、捕獲後の対処、再侵入防止、清掃まで一貫して対応してもらえるので、被害をしっかり防ぐことができるでしょう。
■アライグマの被害で困っているならプロに相談を
毒餌の使用は法律や安全面でのリスクが高いため、アライグマ対策の方法としては現実的ではありません。許可を得たうえでの罠による捕獲、忌避剤による追い出し、侵入口封鎖、そしてプロ業者への依頼など、アライグマ対策にはさまざまな方法があります。
アライグマ対策は法律上の問題や許可取得が必要なケースもあり、専門的な知識がない方が行うには限界があるので、状況に応じてプロに相談することを検討し、アライグマによる被害の拡大を防ぎましょう。
アサンテでは、無料の事前調査や見積もり作成、アフターフォローなど、納得してご依頼いただける体制を整えています。
1. 調査とお見積もりは無料、丁寧に説明
2. 調査・施工・アフターサービスまで自社スタッフが対応
3. 最短で即日対応が可能、土日や祝日も対応
4. アライグマやネズミ、ハクビシンなどさまざまな害獣に対応
5. 長年の実績に基づく適切なアライグマ対策をご提案
大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。