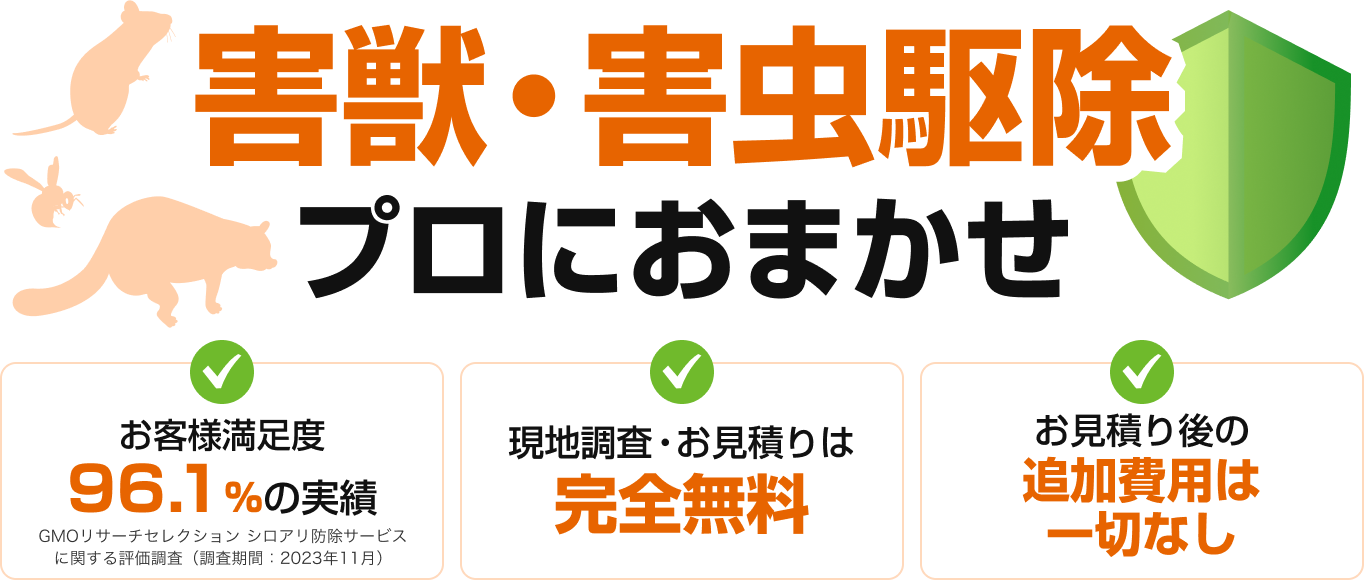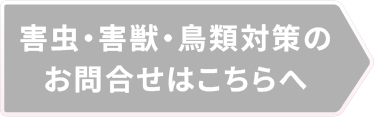ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマのフンを見つけたら要注意?フンの特徴や注意すべきポイントを解説
アライグマのフンを見つけたら要注意?
フンの特徴や注意すべきポイントを解説

屋根裏で見慣れない動物のフンを見つけて、なんの動物のフンだろうと不安を抱えている方はいらっしゃいませんか。アライグマのフンには感染症や悪臭など、さまざまなリスクが潜んでいます。
本記事では、アライグマのフンの特徴から見分け方、放置による被害、適切な対処法まで詳しく解説します。
目次
アライグマのフンを見つけたら要注意?
屋根裏や床下でアライグマのフンを見つけた場合は、健康被害や住宅へのダメージが広がるおそれもあるため、早めの対応が必要です。ここでは、フンによって引き起こされるリスクや、アライグマ特有の排泄の習性を紹介します。
アライグマのフンを放置するリスク
アライグマのフンには細菌やウイルスが含まれている場合があり、感染症につながるおそれがあります。特にアライグマ回虫やレプトスピラ症などは人間にも感染するため注意が必要です。
アライグマ回虫はアライグマの体内に寄生する線虫の一種で、人に感染すると脳や目、内臓に重大な影響を及ぼす場合があります。レプトスピラ症はアライグマの尿などを介して感染し、発熱や筋肉痛などインフルエンザに似た症状が現れる細菌性の感染症です。
そのほかにも、フンを放置するリスクとして以下のようなものが挙げられます。
悪臭やカビの発生
天井材や木材の腐食
ダニやゴキブリの繁殖
衛生面だけでなく、建物にも悪影響が及ぶ可能性があります。
アライグマのフンに関する習性
アライグマは特定の場所に繰り返しフンをする溜めフンの習性がなく、さまざまなところでフンをします。屋根裏や天井裏など、湿気がこもりやすい閉鎖空間では悪臭や汚染が広がる原因になります。
アライグマのフンの特徴

アライグマのフンは、見た目や臭いに独特の特徴があります。
ここでは、大きさや形状、臭いの特徴、発見されやすい場所、ほかの動物との違いを紹介します。
大きさ・形状・見た目
アライグマのフンは長さ5〜15cm程度の円柱状で、先端が丸くなっている傾向があります。太さは人間の親指(約2〜3cm)ほどで、やわらかさや水分量は食べたものによって変わります。
フンのなかに果実の種子や昆虫の殻が含まれることがあり、内容物から食性を推測することも可能です。1本ずつ排泄されることが多く、そのままの形状で残りやすい点もアライグマのフンの特徴です。
強烈な臭いと色のバラつき
アライグマのフンは、腐敗臭やアンモニア臭のような強い悪臭を放ちます。果実や昆虫、生ゴミなどさまざまなものを食べるため、未消化の成分が混ざって異様な臭いになりやすいのが特徴です。
フンの色は黒褐色から灰色まで幅があり、排泄直後は黒っぽく湿った状態で、時間が経過するにつれて乾燥して白っぽく変化します。湿気の多い場所では黒いまま残り、乾燥した場所では灰白色に近づく傾向です。
臭いや色だけでアライグマのフンだと断定することは難しいかもしれませんが、フンから刺激臭が強く感じられ黒っぽくベタついた状態である場合は、アライグマの可能性を視野に入れてよいでしょう。
フンがよくある場所
アライグマのフンは、屋根裏や軒下、天井裏、床下など人目につきにくい場所でよく見られます。特に天井板の裏や断熱材の上は寝床のすぐ近くなので排泄される可能性が高く、臭いや汚れが広がりやすいのが特徴です。
また、ベランダの物陰や物置、空き家の床面など、人の出入りが少ない場所にも排泄されることがあります。フンの位置は、侵入経路や巣の場所を探るうえでの手がかりになります。出入り口の近くや通路になっている場所に排泄するケースもあるため、痕跡のある箇所をたどることで行動範囲を推測することが可能です。
タヌキやハクビシンなどほかの動物との違い
アライグマ・タヌキ・ハクビシンそれぞれのフンの特徴は以下の通りです。
アライグマ
円柱状で比較的太く、先端は丸い
果実の種子や昆虫の殻が混ざることがある
排泄場所が分散する傾向がある
ハクビシン
細長く小ぶりで、形がいびつになりやすい
果物を好むため、甘酸っぱい臭いが残る場合がある
同じ場所に排泄を繰り返す溜めフンの習性がある
タヌキ
やわらかく、形が崩れやすい
植物片が多く混ざることがあり、臭いは強め
溜めフンの習性があり、特定の場所にまとまって残ることがある
似た特徴を持つことも多く、フンだけで動物を見分けるのは困難です。アライグマかどうかを判断するには、足跡や被害の痕跡など周囲の状況も参考にする必要があります。
アライグマのフンを素手で触るのは危険!
アライグマのフンには、人に感染する病原体が含まれている場合があります。
とくに、アライグマ回虫の卵が体内に入ると、視力や運動機能に障害を及ぼすなど、深刻な健康被害につながるおそれがあります。
そのほか、サルモネラ菌やレプトスピラ菌など、直接接触で感染する細菌類も確認されており、素手で触れるのは危険です。排泄後しばらく経っていても感染リスクが残る場合があるため、乾いているように見えても触らないようにしましょう。
もし手に触れてしまった場合は、すぐに石鹸と流水で丁寧に洗い流してください。
不用意に触れることで健康を害する可能性があるため、対応には十分な注意が必要です。
アライグマのフンを見つけたら業者に依頼すべき?
アライグマは攻撃性が高く対処が難しい動物なので、アライグマのフンを見つけたら、清掃や消毒、捕獲や追い出し、再侵入を防ぐための対策などを行ってもらえる業者に相談しましょう。
専門業者を選ぶポイントとして、ペストコントロール協会に加盟している業者なら、専門知識と経験を兼ね備えた業者であると判断できるでしょう。
■アライグマのフンを見つけたら業者に依頼しよう!

アライグマのフンは放置すると室内の衛生環境を悪化させ、感染症の原因になるリスクもあります。屋根裏や床下などで見つかった場合は、侵入や繁殖が進んでいる可能性もあるため、すぐに専門業者に調査を依頼しましょう。
アサンテでは、アライグマのフンに関して以下のように対応しています。
1. フンの状態や場所から侵入経路を推定し、現地調査を実施
2. フン尿の清掃や殺虫など、衛生面に配慮した処理を実施
3. 金網や防獣資材で通気口・軒下などをしっかり封鎖
4. アライグマ以外にもハクビシンやコウモリなどの害獣に対応
5. 作業後の問合せ対応などアフターフォローも万全
大切な家を守るために、アライグマのフンを見かけたら、そのままにせず、アサンテの害獣駆除をご検討ください。