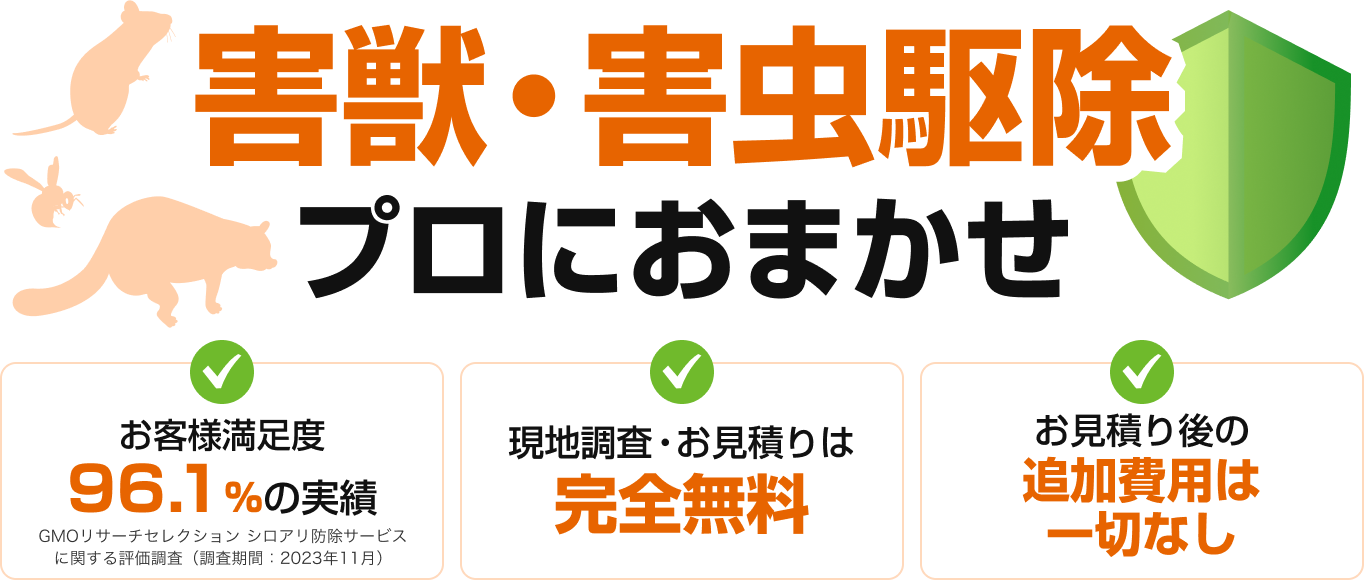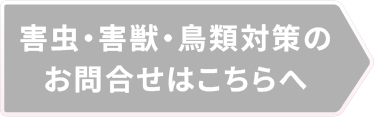ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ハクビシン > ハクビシンの天敵は?人による対策が必要な理由や対処法を詳しく解説します
ハクビシンの天敵は?人による対策が
必要な理由や対処法を詳しく解説します

ハクビシンによる被害にお悩みの方のなかには、天敵の力を利用すればハクビシンが自然にいなくなるのではないかと考える方もいるでしょう。
しかし、天敵を活用した対策は根本的な解決にはならず、ハクビシンの被害を抑えるためには専門的な知識と技術を持った人による総合的な対策をおすすめします。
本記事ではハクビシンの天敵とその特徴、天敵を利用した対策の効果と限界、そして解決のための対処法を詳しく解説します。
ハクビシンの天敵
ハクビシンは東南アジア原産のジャコウネコ科の動物で、本来の自然分布は東南アジア各国を中心とした広い地域です。原産地ではヒョウやオオカミ、大型のヘビなど天敵となる動物が存在しますが、日本では状況が異なります。
アライグマ・キツネ・たぬき

アライグマは、ハクビシンと同じく住宅や健康、農作物に被害を及ぼすおそれがある動物ですが、夜行性であること、屋根裏や人の出入りが少ない廃屋に棲み着くこと、果実や野菜、小動物を食べることなどの共通点が多くあります。そのため、捕食関係がある天敵とはいえませんが、住処や餌場の重複が起こりやすいライバルであるといえます。
キツネやタヌキは雑食で、主な餌は小型哺乳類や昆虫、果実などです。キツネやタヌキも、アライグマと同じく夜に活発に行動することが多く、行動範囲も似通っており、ハクビシンと食料や住処を奪い合うライバルと考えられます。
猛禽類

タカやワシ、ハヤブサやフクロウのような猛禽類は鋭い爪とくちばしを持ち、獲物を捕らえて食べる肉食の鳥類で、ハクビシンの天敵です。
成長したハクビシンは全長約90〜110cm、体重約3〜4kgと体が大きくなるため、猛禽類の捕食対象になりにくいですが、生後間もない子どもが狙われることがあります。
天敵を利用したハクビシンの撃退方法
上述のように、日本においてはハクビシンの天敵といえる動物がほとんど存在しないといえるため、天敵による捕食などでハクビシンの個体数を抑制することは難しいでしょう。
猛禽類の鳴き声を録音してスピーカーで流す、猛禽類を模した置き物で威嚇する、オオカミの尿などのにおいを活用した忌避剤を使用するなどの方法は一時的な効果が期待できますが、ハクビシンは学習能力が高いので慣れてしまう可能性があります。
また、これらの方法に対する効果には個体差があり、個体によっては効果が薄い場合もあります。
ハクビシンは狂犬病などの感染症、ノミやダニなどの寄生虫を媒介している可能性があるだけでなく、噛みつきやひっかきによる怪我のおそれもあるので、威嚇目的で飼い犬や飼い猫をハクビシンに近付けるのは避けましょう。
ハクビシン被害には人による対策が必要な理由
天敵を利用した対策には限界があるため、根本的な解決には人による対策が不可欠でしょう。ここでは、なぜ人による対策が必要なのかを詳しく解説します。
侵入経路の封鎖が必要
ハクビシンは8cm四方または6cm×12cmの穴、円なら直径10cm程度の隙間からも侵入できます。木登りが得意で、屋根の隙間から屋根裏に忍び込むことも可能です。
天敵の存在だけでは追い出すことはできても侵入経路を塞ぐことはできません。壁や軒下の穴、床下通気口、戸袋の下などを金網で塞ぐことや屋根へ伸びる庭木の剪定といった人による物理的な侵入防止策が求められます。
フンの清掃や消毒など衛生対策が必要
ハクビシンは基本的に母仔を中心とした家族単位で生活し、一度棲みつくと複数の個体が同じ場所に出入りする可能性があります。
また、ハクビシンは決まった場所に排泄する習性があり、屋根裏や庭の隅などにフンを蓄積していくことがあります。これらのフンは悪臭の原因となるだけでなく、天井材や床材の腐食、感染症を引き起こします。
こういった衛生上の問題を解決するためには清掃と殺虫作業が必要で、適切な防護具を着用した安全性の高い作業が求められます。
再侵入を防ぐための長期的な管理が必要
天敵への忌避効果を活用した一時的な追い出しでは、根本的な解決にはなりません。
長期的な被害防止には侵入経路の封鎖や衛生管理、ハクビシンを寄せつけにくい環境づくりといった総合的な管理を長期的に行う必要があります。定期的な点検と維持管理、侵入経路の継続的なチェック、餌となるものの除去などの包括的なアプローチには、人による対策が必要です。
ハクビシン被害がある場合の対処法

ハクビシン被害が確認された場合、適切な対処法の選択が必要です。自力での対処と業者への依頼、それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで判断しましょう。
まず自力での対処を検討する場合、ハクビシンに関する法律について知っておく必要があります。ハクビシンは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、無許可での捕獲は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
出典:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(環境省)
許可申請から対処まで時間と労力がかかることや感染症リスク、捕獲後の対応といったことを考えると、業者に依頼することも検討すべきでしょう。業者は法令に則った適切な対応が可能で、感染症のリスクも踏まえて安全性を確保しながら対処してもらうことができます。ハクビシンの知識や被害への対応策などの専門的な知識が豊富なので、プロに任せることでより確実に対策を講じることができるでしょう。
業者への依頼のデメリットとしては、費用がかかることが挙げられます。業者を選ぶ際は、以下のポイントを確認することが大切です。
適切な許可を取得しているか
ハクビシン対策の経験が豊富であるか
見積もりの透明性があるか
迅速、丁寧に対応してもらえるか
ペストコントロール協会に加盟しているか
これらを事前に業者に確認しておくことで、より効果が高いハクビシン対策が可能になるでしょう。
■ハクビシン被害は天敵に頼らず業者に相談を
ハクビシンの天敵について理解し、天敵を利用した対策方法を知ることは、害獣対策の選択肢を広げる意味で有用です。
ハクビシンの天敵である猛禽類の鳴き声やオオカミなどのにおいを利用した忌避効果は一定の効果はあるものの、効果の持続性や個体差、安全性の問題を考慮すると根本的な対策とはいえません。
ハクビシン被害の解決には、侵入経路の封鎖や衛生対策、長期的な管理が必要です。これらは専門的な知識と技術、許可が必要な作業であり、専門的な知識がないまま行うには多くのリスクが伴います。
早期発見と適切な対策で被害を抑えるためには、早い段階で業者に相談することをおすすめします。
アサンテでは、無料の事前調査や見積もり作成、アフターフォローなどを納得してご依頼いただける体制を整えています。
1. 東証プライム上場企業の信頼
2. 経験豊富な害獣対策のプロによる自社施工
3. 害獣防除の対策やご相談、最短即日で対応
4. 無料の診断とお見積りでじっくり検討可能
5. ハクビシン以外の害獣・害虫にも対応
大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。