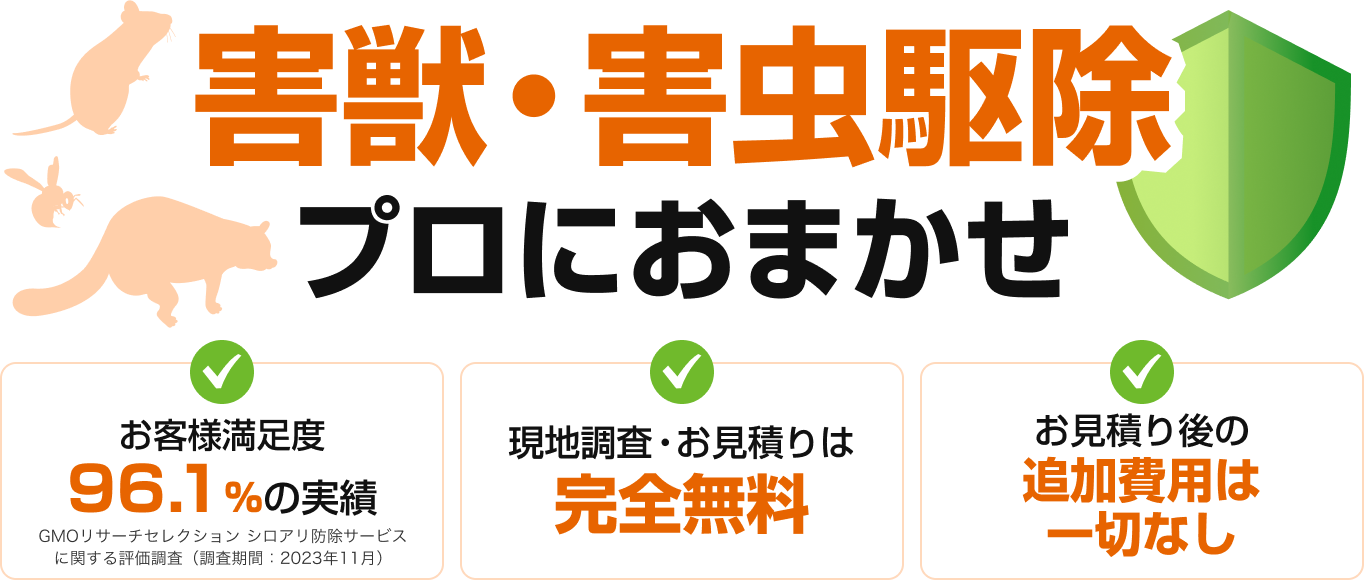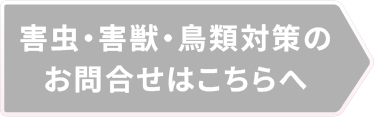ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ハクビシン > ハクビシンの足跡の特徴は?ほかの動物の足跡との見分け方や足跡以外のサインも解説
ハクビシンの足跡の特徴は?
ほかの動物の足跡との見分け方や足跡以外のサインも解説

家の周りで動物の足跡を発見して、どんな動物だろうと対処に困ることもあるでしょう。ハクビシンは日本列島のほぼ全域に分布しており、特に東北地方から中部地方、四国地方で多く確認されています。
ハクビシンは夜行性で姿を見かけにくいため、足跡が存在を確認するための重要な手がかりです。しかし、ハクビシンと似た足跡を残す動物は多く、誤った判断をしてしまうと適切な対策が取れず被害が拡大する可能性が考えられます。
本記事では、ハクビシンの足跡の詳しい特徴やほかの動物との見分け方、足跡以外のサインについても詳しく解説します。
目次
ハクビシンの足跡の特徴
ハクビシンの足跡には、ほかの動物と区別できる明確な特徴があります。以下の3つのポイントを確認しましょう。
足跡の大きさ
ハクビシンの足跡の大きさは、前足と後ろ足のサイズが明確に異なります。前足の幅は約4〜4.5cm、長さは約5cmです。後ろ足の幅も約4〜4.5cmですが、長さは約10cmと前足の約2倍です。
この前足と後ろ足のサイズの違いが、ハクビシンの足跡を特定する際の重要な手がかりです。実際に足跡を発見した際は、サイズを測定してみましょう。大きな後ろ足跡と小さな前足跡がセットで見つかれば、ハクビシンである可能性が高いといえます。
足跡の形状
ハクビシンの足跡は、形状にも特徴的なポイントがあります。
ハクビシンは、5本指で掌球と指が離れているのが大きな特徴です。前足は大きめの肉球が特徴的で、後ろ足は細長い肉球をしており、指球や掌球の跡には丸みがあり、爪跡の有無には個体差があります。

ハクビシンは歩幅が広く、足跡が直線状に並ぶという歩行パターンも、ほかの動物との見分けに役立つポイントです。
足跡や痕跡を残しやすい場所
ハクビシンの足跡を発見しやすい場所を知っておくことで、効率的に確認作業を行えます。ハクビシンは木登りが得意なので、以下のような場所で足跡や痕跡を見つけやすいと考えられます。
樹木の根元
住宅の外壁や柱の周辺
屋根裏やベランダの手すり
雨どいの支柱周辺
庭に設置された排水側溝の縁沿い
特に果樹や畑の周辺、雪や泥のある場所では、足跡がよりはっきりと残ります。ハクビシンは登り降りの際に爪を立てるため、足跡の周辺に爪痕があるかどうかも、ハクビシンかどうかを判断する1つのポイントです。
ほかの動物の足跡との見分け方

住宅街に現れる動物のなかには、ハクビシンと似た足跡を残す動物もいます。間違いやすい動物の足跡の特徴を知っておくと、判別に役立ちます。ハクビシンと間違えやすい動物の足跡の特徴は次のとおりです。
アライグマ:5本指で肉球と指がつながっており、人間の子どもの手形のような形状
タヌキ:4本指で犬の足に似ており、前足と後ろ足の大きさがあまり変わらない
アナグマ:5本指で穴を掘ることが得意なため、長い爪痕がしっかりと残る

足跡の大きさや形状に加えて、発見場所の特徴もあわせて判断すると、よりどの動物か特定しやすくなります。
足跡以外のハクビシン侵入のサイン
足跡だけでは判別が困難な場合、ほかにハクビシンの痕跡がないか確認することも大切です。足跡以外でハクビシンの存在を示すサインには、次のようなものがあります。
糞の特徴:棒状(約5〜15cm)で果物の種やトウモロコシが混じっていることがある
鳴き声:「キューキュー」「キーキー」などの高く連続した声を出す
食害の痕跡:作物を直接かじった跡や果物に大きな穴が開いている
爪痕:木の幹や壁、柱に細くて深い引っかき傷のような跡がある
夜間の騒音:夜中に天井裏や屋根から走る音や動き回る音がする
これらのサインを総合的に判断することが大切です。
ハクビシンの痕跡を見つけるポイント
ハクビシンの痕跡を見つけるためには、ハクビシンの行動リズムを把握するのが重要です。
ハクビシンは夜行性の動物で、日没1時間後頃から明け方まで活動します。ハクビシンが夜間に活動した直後の時間帯、特に雨上がりや雪が降った翌朝は、足跡がはっきりと残っていることがあります。
足跡が判別しづらい場合は、家の周りに小麦粉や石灰などの粉を薄く撒いておくと足跡が残りやすくなり、どこを伝って移動したかを追跡しやすくなります。
夜間のチェック方法としては、センサーカメラの設置が効果的です。人感センサー付きのカメラを侵入が疑われる場所に設置することで、ハクビシンの行動パターンや侵入経路を詳しく把握できます。
カメラは木の根元や雨どい周辺、果樹の近くなど、足跡が発見されやすい場所に設置しましょう。
また、水辺の確認も重要なポイントです。ハクビシンは側溝や用水路、庭の池などの水辺を移動経路として利用します。これらの場所の重点的なチェックで、ハクビシンの存在を確認しやすくなるでしょう。
定期的な観察を続けることで、ハクビシンの行動パターンを把握し、適切な対策を立てることに役立ちます。
ハクビシンの足跡や痕跡を見つけたときの対処方法

ハクビシンの足跡や痕跡を見つけた場合は、早急な対処が必要です。ハクビシンは鳥獣保護管理法により保護されているため、適切な手順を踏んで対策を行います。
まず重要なのは、ハクビシンに直接触れないようにすることです。野生動物は、狂犬病やエキノコックスなどの感染症やノミ、ダニなどの寄生虫を保有している可能性があります。痕跡を確認する際も手袋を着用し、清潔を保つようにしましょう。
初期対応として効果的なのは追い出し作業です。ハクビシンは嗅覚が敏感なため、忌避剤などの嫌いな匂いを用いると効果的です。これらを天井裏や侵入口に設置することで、追い出し効果が期待できます。
侵入経路の封鎖も重要な対策です。ハクビシンは8cm四方または6cm×12cmの穴、円なら直径10cm程度の小さな隙間からでも侵入できるので、壁や軒下の穴、床下通気口、戸袋の下などは金網で塞ぎ、屋根に届く庭木の枝はこまめに剪定しましょう。
こういった対策を効果的に行うためには、ハクビシンの生態に関する専門的な知識が必要なので、ハクビシンの痕跡がある場合は早めにプロの業者に連絡することが重要です。
ペストコントロール協会に加盟している業者なら、技術研修や資格制度に基づく水準が保証されているため信頼性が高いと考えられます。
自力での対処が困難な場合や被害が深刻な場合は、プロの業者への相談をおすすめします。
■ハクビシンの足跡を見つけたらプロの業者にご相談を
ハクビシンの足跡の特徴を理解し、ほかの動物との見分け方を知ることで、適切な害獣対策の第一歩を踏み出せます。ハクビシンの被害は放置すると深刻な問題に発展する可能性があるので、早期発見と対策が被害を抑える鍵となるでしょう。
アサンテでは、無料の事前調査や見積もり作成、アフターフォローなどを納得して依頼できる体制を整えています。
1. 東証プライム上場企業の信頼
2. 害獣対策のプロによる自社施工
3. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全
4. 害獣防除の対策やご相談に最短即日で対応
5. 無料の診断とお見積りでじっくり検討可能
大切な住まいを守るために、アサンテの害獣対策をご検討ください。