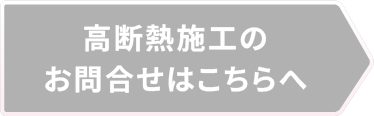ホーム > 戸建て住宅の断熱リフォーム > 床下断熱材がない家の見分け方|住宅の断熱性能をチェックする方法
床下断熱材がない家の見分け方|住宅の断熱性能をチェックする方法
2025/9/22
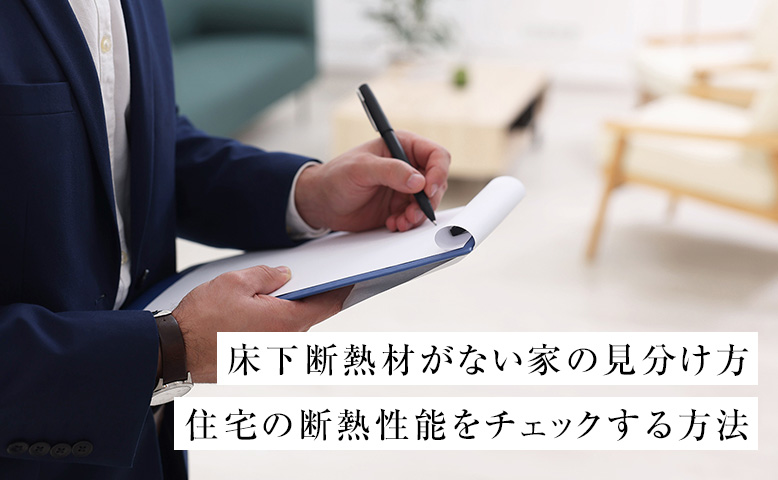
冬になると足元が寒かったり、暖房をつけてもなかなか部屋が暖まらなかったりすると、
「うちの床には断熱材が入っているのかな?」
「断熱材は入っているはずだけど、ちゃんと足りているの?」
と感じる方もいるのではないでしょうか。
とくに築年数のたっている住宅では、床下の断熱材の性能が低かったり、そもそも入っていなかったりするケースもめずらしくはありません。
床下断熱材の有無は、住宅の快適性や光熱費に大きく影響します。
しかし床下はふだん目にすることがない場所のため、断熱材があるかどうかを確認したことがない方も多いでしょう。
この記事では、床下断熱材がない家の見分け方について、誰でも実践できる確認方法から専門的な診断まで紹介します。
また断熱材に問題があるケースや対策方法、賃貸住宅での確認方法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 1 床下断熱材がない家の見分け方|確認方法とは
- 1.1 床の温度差を体感で確認する
- 1.2 家の設計図や仕様書などで断熱材を確認する
- 1.3 床下の断熱材を目視で確認する
- 1.4 専門家に床下の断熱材を診断してもらう
- 2 賃貸住宅で断熱材の有無を確認する方法
- 3 床下断熱に問題があるケース|チェックポイント5選
- 3.1 古い家なので断熱材なし
- 3.2 断熱材が落下している
- 3.3 断熱材を入れる場所が間違っている
- 3.4 断熱材の材質や厚みが適切か
- 3.5 断熱材の施工不良がないか
- 4 床下に断熱材がない場合のデメリット
- 5 床下に断熱材が入ってない場合のおすすめ対策|リフォームで後入れする
- 6 床下断熱材がない?疑問質問にお答えします
- 6.1 Q. 築何年くらいから床下断熱材がない可能性が高いですか?
- 6.2 Q. 賃貸でも大家さんに断熱リフォームを要求できる?
- 6.3 Q. 床下断熱材の後付けリフォーム費用はいくら?
- 7 床下の断熱材が気になったら|まずはアサンテの無料相談をご利用ください
調査・御見積 無料!お気軽にお問い合わせください。
メールでのお問合せ
お問い合わせする床下断熱材がない家の見分け方|確認方法とは

床下断熱材の有無を確認する方法は、かんたんなものから専門的なものまであります。
今回は4つの方法を紹介しますので、まずは手軽にできるものから試してみて、必要に応じてよりくわしい確認を行うとよいでしょう。
床の温度差を体感で確認する
もっともかんたんな確認方法は、実際に床の温度を体感で確認することです。
とくに冬場は断熱材の有無による違いが顕著に感じられます。
朝起きたときや外出先から帰宅した直後など、暖房を使用していない状態で床を素足で歩いてみましょう。
断熱材がないと、床がひんやりと冷たく感じられ、足裏から体温が奪われる感覚があります。
ただし、この方法はあくまで目安であり、断熱材の有無や状態を確実に判断することはできません。
家の設計図や仕様書などで断熱材を確認する
住宅を購入した際に受け取った設計図や矩計図(かなばかりず)、仕様書などの図面があれば、断熱材の有無を確認できます。
これらの書類には、使用されている断熱材の種類や厚さ、施工箇所が記載されているからです。
- 断熱材の施工部位
- 断熱材の種類
- 断熱材の厚さ
- 断熱材の適合する規格
- 熱伝導率 など
確認すべき書類は、建築確認申請書、設計図書、仕様書、竣工図などです。
とくに「断熱仕様」「断熱工事」といった項目を探してみましょう。
床下断熱については「1階床断熱」「基礎断熱」などの記載があるはずです。
図面の見方がわからないときは、建築会社や不動産会社、リフォーム会社などに問い合わせることをおすすめします。
また中古住宅の場合は、前の所有者から引き継いだ書類を確認しましょう。
ただし築年数が古い住宅では、そもそも断熱材に関する記載がないこともあります。
床下の断熱材を目視で確認する
断熱材を確認するうえでもっとも確実な方法は、実際に床下をのぞいて断熱材を目視で確認することです。
多くの住宅には、キッチンや洗面所の床に点検口が設置されているので、そこから床下へ入ります。
点検口から床下へ入る際は、懐中電灯を用意し、埃やカビを吸わないようにマスクを着用、汚れてもいい服装で行いましょう。
断熱材がある場合、床の裏側にグラスウールや発泡スチロール系の断熱材が取り付けられているのが見えます。
ただし床下は狭くて暗い空間のため、全体を確認するのは困難です。
また釘やガラスなどの鋭利なもの、カビや害虫などが発生している可能性もあるため、無理をせず安全に配慮して確認しましょう。
点検口がない場合は、畳を上げて確認する方法もありますが、専門知識がいるため慎重に行う必要があります。
専門家に床下の断熱材を診断してもらう
自分で確認するのがむずかしかったり、確認してもよくわからなかったりする場合には、専門家への依頼をおすすめします。
リフォーム会社や住宅診断士(ホームインスペクター)、建築士、などが床下診断サービスを提供していることが多いでしょう。
専門家による診断では、断熱材の有無だけでなく、以下のような点についても総合的にチェックしてもらえるでしょう。
- 床下断熱の施工状態
- 床下断熱材の劣化具合
- 湿気やカビの発生具合
- シロアリ発生の有無 など
プロの診断であれば床下のすみずみまで確認してもらえるため、安心できるでしょう。
診断費用は5,000~10,000円程度が相場ですが、専門の業者によっては、調査や診断は無料で行ってくれるところもあります。
点検口がない場合には、点検口作成のための追加料金が必要になるケースもあります。
賃貸住宅で断熱材の有無を確認する方法

ここまでは、持ち家に関する断熱材の確認方法を紹介しました。
賃貸住宅についても、断熱材の有無は気になるところです。しかし賃貸住宅の場合、勝手に床下を確認することはできません。
まずは、物件情報や重要事項説明書をチェックしましょう。
築年数が新しい物件では「高断熱仕様」「省エネ基準適合」などの記載がある場合もあります。
また、不動産会社や大家さんに直接質問することも可能です。
「床下に断熱材は入っていますか」と率直に聞いてみましょう。
内見時には、可能であれば素足で床を歩いてみて、冷たさを確認します。
また、前の入居者の光熱費を参考にするのもひとつの方法です。
同じ広さの物件と比較して光熱費があまりにも高い場合は、断熱性能が低い可能性もあります。
賃貸住宅で断熱性能に不満がある場合には、まずは管理会社や大家さんに相談してみましょう。すぐに改善はむずかしくても、今後のリフォーム計画に反映してもらえるかもしれません。
床下断熱に問題があるケース|チェックポイント5選

床下断熱材は、ただ入っていればいいというものではありません。
施工状態などにより、じゅうぶんな断熱性能を発揮できていないケースも多々あります。
これからあげる5つのポイントをチェックしてみましょう。
古い家なので断熱材なし
1980年以前に建てられた住宅では、そもそも断熱材が使用されていないケースも多くあります。
日本では1980年に省エネルギー基準が制定されてから、徐々に断熱材の使用が一般的になりました。
しかし、この時期の基準も現在と比べると低く、十分な断熱性能とは言えません。また、努力義務であったため、断熱材が無い住宅も多くあります。
築40年以上の住宅で床下の断熱材が気になる場合には、一度床下の確認をすることをおすすめします。
たとえ断熱材がない場合でも、後から追加できるかもしれません。
断熱材が落下している
断熱材が入っていても、はがれて落下しているケースもよくあります。
とくにグラスウールなどの繊維系断熱材は、固定が甘いと落下してしまうことも。
断熱材の落下は、施工不良や木材の木やせ、振動などが原因で起こります。
一部でも落下していると、その部分から熱が逃げてしまうのです。
床下点検の際は、断熱材がしっかりと固定されているか、落下している箇所がないかを確認しましょう。
断熱材を入れる場所が間違っている
断熱材は適切な場所に施工されていないと、十分な効果を発揮しません。
床下断熱の場合、床の直下にすきまなく施工する必要があります。
また部分的にしか施工されていない場合には、断熱不足となり、思うような断熱性能が得られません。
正しい施工位置は、床組(根太や大引)の間に、床板の裏側にできるだけ密着するように取り付けることです。
断熱材の材質や厚みが適切か
断熱材にはさまざまな種類があり、それぞれ必要な厚さが異なります。
古い住宅では、たとえ断熱材が施工されているとしても、現在の基準から見ると断熱材が薄すぎることもあるのです。
たとえば一般的なグラスウールの場合、現在の省エネ基準では100mm程度以上の厚さが必要ですが、20年前は50mm程度でも十分ともいわれていました。
また安価な断熱材を使用している場合、密度が低く断熱性能が劣ることもあります。
使用されている断熱材の種類と厚さを確認し、現在の基準と比較してみましょう。
不足している場合は、追加施工を検討するのもおすすめです。
断熱材の施工不良がないか
断熱材が正しく施工されていないと、本来の断熱性能を発揮できません。
施工不良の例として、断熱材同士にすきまがある、配管や配線周りの断熱材不足(すきまができている)、固定不良などがあります。
とくに注意すべきは、断熱材のすきまです。わずか数センチのすきまでも、そこから熱が逃げてしまい、全体の断熱性能を大きく低下させてしまいます。
また、床下の配管や配線の周りは施工がむずかしく、断熱材が省かれているケースも。
プロの診断なら、これらの部分もチェックしてくれるはずです。
床下に断熱材がない場合のデメリット
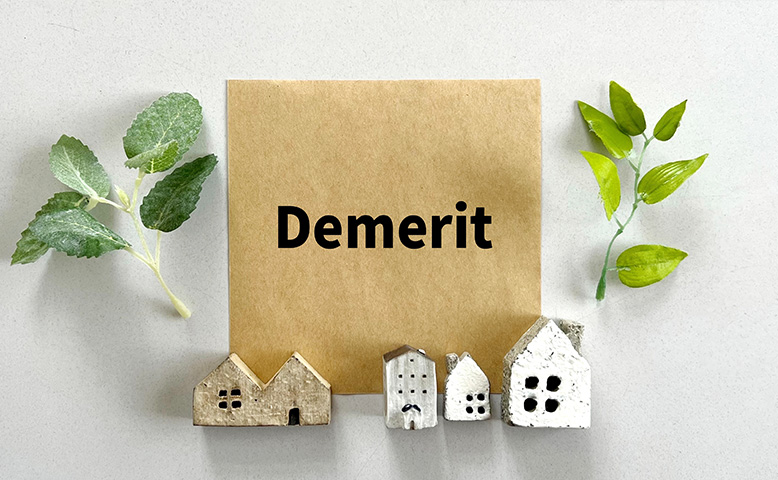
床下断熱材がない、または不十分な場合には、さまざまなデメリットが生じます。
単に寒さや暑さを感じるだけでなく、経済的な負担や健康への影響も考えられるのです。
もっとも大きなデメリットは、光熱費が高額になることでしょう。
断熱性能が低い住宅では、冬は暖房費が、夏は冷房費が増加しがちです。
一般的に断熱性能が低い住宅では、適切に断熱された住宅と比較して年間の光熱費が高くなるといわれています。
また、室内の温度差により結露が発生しやすくなることも。
結露はカビの原因となり、アレルギーや呼吸器系の健康被害を引き起こす可能性があります。
快適性の面でも、足元の冷えによる不快感や、部屋ごとの温度差によるヒートショックのリスクなど、日常生活に支障をきたす場合もあるのです。
床下に断熱材が入ってない場合のおすすめ対策|リフォームで後入れする

床下断熱材がない、または不十分な場合、リフォームによる後付けがもっとも効果的な対策でしょう。
床下断熱リフォームは、(工法にもよりますが)比較的かんたんに施工ができ、費用対効果も高い改修工事になります。
一般的な施工方法は、床下空間に入って床下側から断熱材を取り付ける方法です。
費用は施工面積や使用する断熱材によって異なりますが、延床面積100㎡程度の住宅で15~30万円程度が相場となっています。
部分的な施工も可能で、とくに寒さを感じるリビングや寝室だけを優先的に施工することも可能です。
床下断熱材がない?疑問質問にお答えします
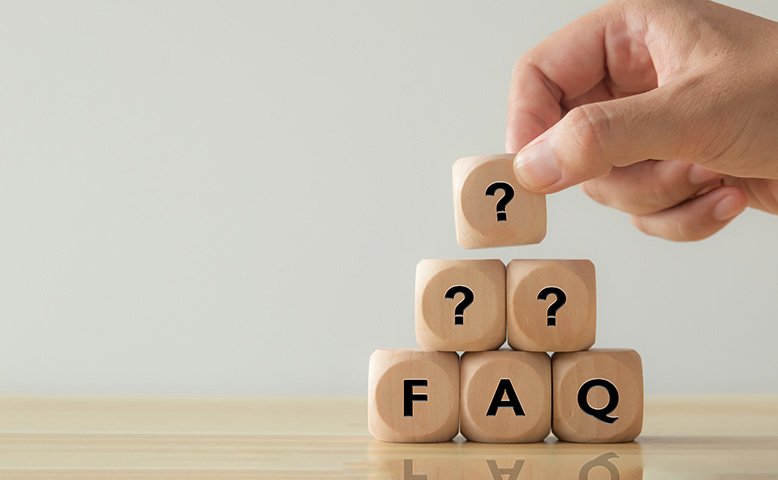
ここからは、床下断熱材の有無に関する疑問質問にお答えします。
Q. 築何年くらいから床下断熱材がない可能性が高いですか?
築40年以上(1980年以前)の住宅では、床下断熱材が入っていない可能性が高いです。1980年に初めて省エネルギー基準が制定されましたが、当時はまだ義務ではありませんでした。
1992年の新省エネ基準、1999年の次世代省エネ基準と段階的に強化され、2025年からは全ての住宅で一定以上の断熱性能を持たせることが義務化されました。
築年数が新しくても、ローコスト住宅では断熱材が省略されているケースもあるため、実際に確認することが大切です。
賃貸でも大家さんに断熱リフォームを要求できる?
既存住宅では法的に断熱材設置が義務というわけではないため、大家さんへ断熱リフォームを強要することはできません。
しかし交渉の余地はあるでしょう。
まず、冬の光熱費が異常に高い、結露やカビが発生するなど、具体的な問題点を文書で伝えましょう。
断熱改修により物件の資産価値があがることや、入居率の改善につながることを説明すれば、大家さんも前向きに検討してくれるかもしれません。
すぐに対応してもらえない場合は、他の物件への引っ越しも選択肢のひとつとなるでしょう。
Q. 床下断熱材の後付けリフォーム費用はいくら?
床下断熱材の後付けリフォーム費用は、一般的に1㎡あたり3,000~5,000円程度です。
しかし使用する断熱材の種類により価格は変動し、グラスウールなら比較的安価、発泡ウレタン吹き付けなら高めになります。
また床下の状況により、たとえば湿気対策の防湿シート施工や、床下換気などの追加工事が必要となることもあるでしょう。
正確な費用は、業者から見積もりをとって検討しましょう。
床下の断熱材が気になったら|まずはアサンテの無料相談をご利用ください

床下断熱材の有無は、住宅の快適性と省エネ性能を大きく左右する要素です。
こちらの記事で紹介した4つの確認方法を参考に、まずはご自宅の床下断熱の状態をチェックしてみましょう。
体感での確認から始め、可能であれば図面の確認や目視での点検を行い、必要に応じて専門家の調査を受けることで、正確な状況を把握できます。
もし断熱材がない、または不十分な場合は、リフォームによる改善の検討がおすすめです。
床下のプロ、アサンテでは無料で床下の診断を行っていますので、まずは床下断熱材の状況を知るためにもお気軽にご相談ください。
調査・御見積 無料!お気軽にお問い合わせください。
メールでのお問合せ
お問い合わせする