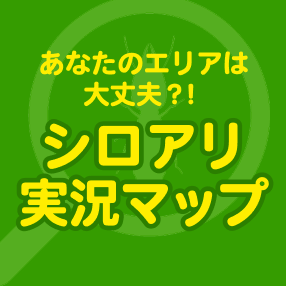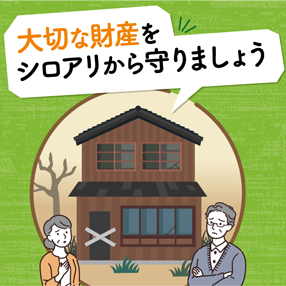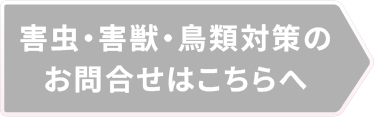ホーム > これでもう怖くない!害虫・害獣対策ガイド > 蜂 > 蜂の種類とその生態について
蜂の種類と
その生態について
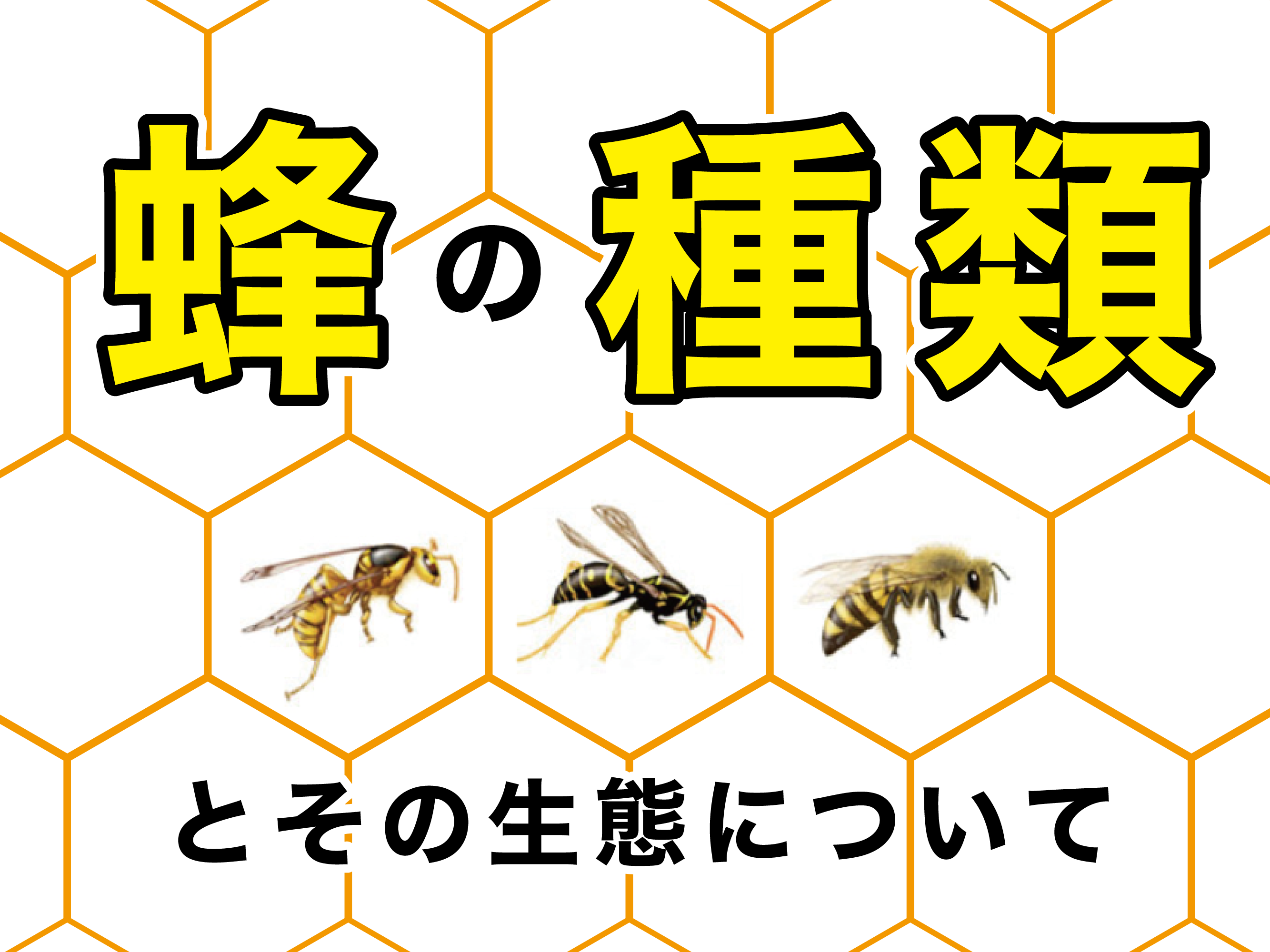
日本の蜂は多様で、4,000種類ほどの蜂が生息していると言われています。私たちの身近に生息する昆虫ですが、その種類や生態は意外と知られていません。中には、人間に危害を加える危険な蜂も存在します。
本記事では、様々な蜂の種類について解説し、蜂との正しい付き合い方について考えていきます。
主要な蜂の種類一覧と特徴
日本に生息する蜂のなかで、人間を刺す主な種類は主に以下の3種類です。
ミツバチ
スズメバチ
アシナガバチ
見た目はもちろん、行動や巣の作り方などにもそれぞれ特徴があります。以下で、それぞれの特徴を見ていきましょう。
ミツバチ
ミツバチは、蜂蜜を生産するだけでなく、農作物の受粉を助けるなど、人間にとって非常に重要な役割を担っています。しかし、ミツバチは巣を攻撃されると反撃してくることがあります。刺されると痛みやかゆみを引き起こすため、注意が必要です。
ミツバチは春から夏に活発に活動し、六角形の巣を作ります。巣は木の空洞や住宅の天井裏や床下などの閉鎖空間に作られ、コロニーの成長とともに拡大していきます。冬は女王バチと働きバチが巣で一緒に越冬します。

セイヨウミツバチ 体長1.3cm
スズメバチ
スズメバチは、攻撃性と強力な毒から極めて危険な蜂です。オオスズメバチ、キイロスズメバチ、コガタスズメバチが特に危険とされ、中でもオオスズメバチは体長40mmに達する日本最大の蜂です。
巣を守るために攻撃的になり、5月から9月は特に注意が必要です。
スズメバチの巣は球形で、特徴的なマーブル模様の外皮に覆われています。住宅の庭(地中)や軒下、外壁、換気扇口など様々な場所に作られ、種類によって巣の場所が異なります。

キイロスズメバチ 体長2cm
アシナガバチ
アシナガバチは、スズメバチに比べて比較的おとなしい蜂です。その名の通り長い脚が特徴で、体長は15mmから30mm程度です。攻撃性が低く、人を刺すことは稀ですが、ミツバチ同様、巣を刺激すると攻撃してきます。
巣は木の枝や軒下、戸袋などに垂れ下がる形で作られ、シャワーヘッドのような独特の形状をしています。冬は基本的に女王バチのみが越冬しますが、種類によっては働きバチも一緒に越冬することがあります。

セイヨウミツバチ 体長1.3cm
特徴から見る蜂の種類
上記では、人間を攻撃しやすい蜂の種類を紹介しました。しかし、多くの場合、どこにいる蜂がどの種類なのかを判断するのは困難でしょう。
そこで、以下では特徴別に蜂の種類を紹介します。
屋根裏に巣を作りやすいのはスズメバチやミツバチ
軒下や屋根裏に巣を作る主な蜂は、スズメバチとミツバチです。これらの場所は蜂にとって安全で快適な環境であるため、巣作りに適しています。
また、スズメバチの中でも、特にヒメスズメバチ、モンスズメバチ、キイロスズメバチの3種類が軒下などに巣を作る傾向があります。ミツバチも同様に、床下や軒下に巣を作ることがあります。
日本で一番強い蜂はオオスズメバチ
日本に生息する蜂で一番強いのは、オオスズメバチと言われています。強い毒性、大きな顎による噛む力、高い攻撃性があるためです。
秋には他の蜂の巣を襲うこともあるほど狂暴です。オオスズメバチは非常に危険なため、遭遇した場合は絶対に自力で駆除せず、必ず専門家に依頼してください。
無毒な蜂の種類
蜂の中には、人間に無害な種類も存在します。蜂は体の構造によって分類され、広腰亜目のハチや有錘類のハチは人を刺す性質がありません。これらのハチは、人間と安全に共存できる昆虫です。
一方、細腰亜目の有剣類に属するスズメバチやアシナガバチは、強い毒性を持ち、人を刺す危険性があります。
人を刺さない蜂の種類
日本には刺さない蜂も多く存在します。代表的な刺さない蜂は、以下のとおりです。
クマバチ
マルハナバチ
ハバチ
ジガバチ
これらの蜂は、害がないことが多いです。
蜂の種類と生態を理解して共生しよう
「蜂に刺されると痛いし、怖い……」このように、蜂は怖い存在とされていますが、地球の生態系に不可欠な生き物です。
蜂は植物の受粉を助け、生物多様性の維持に貢献しています。そのため、蜂の生態を理解し、適切な距離を保ちながら、共生することも大切です。
蜂は、有益な昆虫でもあります。
ミツバチがハチミツを作ることや、植物の受粉を手伝う益虫であることはよく知られています。そして、アシナガバチやスズメバチは害虫を捕食してくれる益虫でもあります。
蜂は生態系において重要な役割を担っているため、むやみに駆除するのではなく、共存の道を探っていきましょう。
蜂と人間が共生するためのポイント
人間と蜂の共生には、蜂の種類に関わらず、人間の生活動線に近づかせないことが大切です。不必要な接触や衝突を避け、両者の安全を確保すれば、決して危険なだけの昆虫ではありません。
以下に、蜂と共生するためのポイントを解説しますので、参考にしてください。
餌になるものを減らす
ミツバチが好む花を庭に植えないようにする、アシナガバチが好む虫を見かけたらこまめに駆除する、スズメバチが食べないようゴミの管理を徹底するなど、餌になるものを減らすのが効果的です。
特に生ごみの適切な処理と、甘い飲食物の速やかな片付けは有効です。缶の飲み口や底に残るわずかなジュースにも注意してください。
巣が作られていないか定期的にチェックする
春から初夏の蜂が巣作りを始める時期は、定期的な点検を行ってください。これにより、巣が小さいうちに適切な対処ができます。
具体的な点検場所には、天井裏、床下、軒下、物置き、カーポート、庭の植栽などがあります。定期的にチェックすることで、蜂の巣を早期に発見できます。
こまめな点検習慣を身につけ、蜂との不要な接触を避け、安全な生活空間を確保しましょう。
蜂への刺激を減らす
スズメバチの攻撃を避けるには、その習性を理解するところから始めましょう。スズメバチは濃い色や強い香りに反応しやすい傾向があります。
そのため、春から夏の活動期間中は、濃い色の服を避け、香水などの強い香りのする製品の使用を控えてください。また、スズメバチを見つけた場合には、急な動きをせず、静かに行動しましょう。
生活に支障がないならそっとしておく
人間の生活にさしさわらないならそっとしておくという選択肢もあります。ミツバチやアシナガバチは比較的温厚で、刺激しなければ攻撃する可能性は低いです。これらの蜂が庭に飛来しても、過剰に恐れる必要はありません。
ただし、スズメバチの巣がある場合や、子供・ペットがいる環境、近隣への影響が懸念される状況では、対策が必要です。
対応に迷ったら、プロの業者に相談してみるとよいでしょう。特に都市部や住宅地では、蜂の益虫としての側面はあまり重視されませんので、放置することでトラブルになる可能性があります。
農村地域ならご近所さんに相談を
「ミツバチがよく飛んでくると思ったら、ご近所さんが養蜂家だった」
農村地域ではそんなケースもあります。農作物の害虫を食べてくれる益虫として、アシナガバチやスズメバチをあえて駆除しない農家さんもいます。
蜂が益虫として大切にされている地域では、駆除することがかえってご近所トラブルの原因になることもあります。
まずはご近所さんに状況を共有してみましょう。ただし、自身の生活に危険が及ぶのであれば、駆除することを優先してください。
■蜂の種類まとめ
蜂の種類、自分たちのライフスタイル、住まいの地域の特性など、さまざまな要素が蜂への対処方法を左右します。
蜂の種類や生態を理解し、適切な対応をとることで、蜂との共存は可能です。もし蜂の巣を発見したり、蜂に刺されたりした場合は、慌てずに専門業者に相談することをおすすめします。